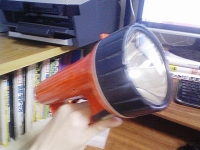「面白い度☆☆☆☆☆ 好き度☆☆☆」
私とメロディはこっち!ブロッサムとピーチはあっち!ドリームとブルームはそっちをお願い!
プリキュア三度目の大集合!なんと
総勢21人!
「いつの間にかすごい数だな」「そりゃこんだけいるんですもの」「まだいても不思議じゃないわね」
なんという
メタ発言!
いや面白い!面白いの種類が違う気がするけど
…面白い!あれだね、
ある種の宝塚歌劇団だと思えばいいんだね。
普通21人のキャラクターなんてどう考えたって1時間ちょいの作中で
まともに動かせるわけないんだから、一体どうやるんだろうって思ってたら、なんとまあスタッフはなかなかの理系。
因数分解しやがった。
これはたけしさんも自身の映画で実践している理論なんだけど、映画のシーケンスって似たシーンごとにまとめられて省略がきくんですよ。
だから最初の被害者が銃で撃ち殺されるシーンを見せたら、次の二番目三番目の殺しは死体のショットを入れるだけで、見ている人は何が起きたか想像ができてしまう。別に殺しのシーンを何度も繰り返す必要はないってこと。
同じくプリキュア21人も作中の役割ごとに大きく三つのグループに分けて三人のプリキュアみたいに動かしてしまったという・・・
例えば海のエリアで戦う羽目になったグループはみんな参謀役というか二番手で、誰も先陣切って戦おうとしない
悲しき副部長の性が・・・!
こういう作り手の顔(多分悩みw)が見える作品って私大好きで「よくまあこんな手法をひねり出したなあ」って感心しました。
とはいえ
やっぱり21人いることにはかわりがないので
(つーか誰が喋ってんねん苦笑)、物語の展開は前作以上に荒削り。
前作で多少は描いていた説明(「え?私の他にもプリキュアが!?」という絶対必要だが面倒なシーン)とかもうどうでもよくなったのか、つるべ落としのようにガンガン進めちゃってるwひどいww
そういったメタ的なツッコミが入るっていうのは作り手側も十分意識していて、この映画を大きなお友達が見ることをちゃんと想定しているんだよね。笑われているわけじゃない。しっかり笑わせているんだ。
みんな上手く着地するのに
一人海へダイブするキュアマリン。みんなかっこよく構えているのに
ローワン・アトキンソンのような動きのキュアマリン。wwwポ、ポーズ、それでいいの?ww
最後に一言。動物仲良し対決、
敵と一緒にペットも消滅しているんですが・・・
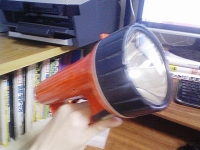
プリキュアがんばれー。