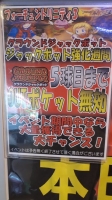FT4への以降は3月に入ってすぐってわけでもなさそうなんですが、一応区切りということで最終成績を振り返ってみました。このゲームにハマって2年2ヶ月・・・!ファーストアウトは何回出たのか!?
 ジャックポット総合
ジャックポット総合
ジャックポットの回数は、3色あわせて435回。うち、ワールドが173回、グラウンドが143回、もっとも苦手なオーシャンが119回でした(最後の最後でちょっと追い上げたな)。
ジャックポットの獲得ウィンの合計は137万1128枚。大きすぎていまいちわからん。
オーシャンジャックポット
オーシャンジャックポットチャンスには1280回挑戦しています。
で、119回ジャックポットを出しているので、ジャックポット確率は約1割、9.3%ということになりました。穴の数が12個もある割には若干健闘したか・・・!?
オーシャンジャックポットと言ったら忘れちゃいけない倍率の内訳。
×1は30回でジャックポット全体の25%。
×2は48回でジャックポット全体の40%。
×4は41回でジャックポット全体の35%。
2倍オーシャンってあんまり取っているイメージがないんだけど、一番多かったのか。意外。
さらに、海龍神の一撃、すなわち4500枚以上のオーシャンジャックポットは50回とっています。つまりオーシャンジャックポットの4割以上はスタッフロールになっているという。そりゃ、なかなかジャックポット出ないわ。
グラウンドジャックポット
グラウンドジャックポットチャンスには1170回挑戦しています。
で、143回ジャックポットを出しているので、ジャックポット確率は12.2%ということになりました。まあまあ高い確率の割に勝てているイメージがないのは、そのジャックポットのほとんどが限界を突破していないからであろう。
実際、大地神の連撃、すなわち4500枚以上のグラウンドジャックポットはたったの7回(ジャックポット全体のわずか5%)しか出せていません。佐野の9500枚の衝撃が強すぎだけど、実はグラウンドジャックポットによるスタッフロールはめちゃくちゃ難しいことがわかる。
さて、お楽しみのファーストアウトの回数は
驚異の214回。つまり、ジャックポットチャンスのうち18%という高確率で3球でゲームオーバーをしている。まあ、20個穴がある中の4個OUTがあるわけだから、確率的には順当ではあるか。
逆に、10球以上粘った回数は223回でチャレンジ中の19%ということになりました。1/5をかわし続けるわけだから、これも妥当かな。
※10球到達する確率は65536/390625(8回アウトをかわす)で、だいたい1/6。
さらに、ネクストオーシャンは4回。うち1回はオーシャンジャックポットの×2が取れました。マジで奇跡。
ネクストワールドはずっと多く14回も出ているのに、ネクストワールドジャックポットをとることはできませんでした・・・
ワールドジャックポット
私が佐野時代に最も強かったやつ。
ワールドジャックポットチャンスには1214回挑戦しています。
で、173回ジャックポットを出しているので、ジャックポット確率は14%ということになりました。勝率1割を超えている。さすがである。
もっと言えば、2回ほどバグでジャックポットを無効にされたことがあるので、多分ジャックポットは175回は越えていると思う。
ひとつめは
センサーがジャックポットをスルー。もうひとつは6であがりだったのに5にされて内周から排除されたことがあります。CONMAIの闇を感じたわ。
太陽神の進撃、すなわち4500枚以上のワールドジャックポットは意外と少なく25回(ジャックポット全体の14%)。ただ、4000枚代はかなりとっていると思う。今日もとってたし。
また、ファーストハント、つまり初球でのジャックポットは76回あるそうです。なんと全ジャックポットの44%が初球。惜しむらくは、ジャックポットワープの称号がないため、ワープしてジャックポットをとっている回数がわからないこと。ただし、
ワープのジャックポットはかなり多いと思われます。
さらに、自分の陣地には755人のプレーヤーさんが止まってくれ、自分自身も44回止まっています。
レジェンドモード
レジェンドモードは課金で突入したのも合わせて123回行っています。
うち、天然ものは43回。どんだけ課金で行ってんだ。
最高獲得枚数は3番ステーションで28ラウンド継続した時の8770枚。これ全国2位とかだった気がする。
逆にたった2ラウンドで終了した悲劇は
なんと6回もあった。※うち1回は忘れもしねえ
札幌のすすきの。
スカイルーレット
チャンスボールは2325個落としていました。
課金もあるので、純粋なスカイチャンスからの挑戦ではないものもあるけれど、スカイルーレットは658回回しています。
うち、オールスカイルーレットは63回だったので、約1/10の確率でオールスカイルーレットが発生するっぽい。意外と高いのね。
その他
TRICは・・・
オーブを7871個獲得し・・・
確変に1533回突入し・・・
2645回超確変に突入し・・・(超確変の方が多い!!???)
221回超確変で5連チャン以上し(最高連チャン数は佐野での24連チャン)・・・
393回のダブルウィンと・・・
93回のトリニティウィンと・・・
10409個の青クリスタルと・・・
10157個の赤クリスタルと・・・
10688個の黄クリスタルを獲得し・・・
28人の女神に祝福され・・・
265人のリュートとヴィオラが虹を描き・・・
138回オーブ君が全回転し(うち、777が確か1回)・・・
246回ロゴが落下し・・・
261回虹色文字演出が出て・・・
どっちか選べで
7球のオーブくんと
4体のハニ太郎と
3頭のわかばちゃんと
2羽のアニマと
2匹のブーニャと
3羽のシリウサと
4体のまつり君と
1匹のチェシャネコが降ってきました。
※チェシャネコは多分トイレ行っている時に降ってきてるな。
記憶にないもん。
また、スロットでは
1776回ゴールし・・・
182回ゴールボーナスで×10を出し・・・
ノーボーナス30を2676回も出し・・・
ステーションチャレンジ10回連続失敗を335回もしています。
鋼のハートだろ。
逆に、スナイパーは752回しているんだけど、
ステーションチャレンジの回数がカンストしているので、一体全体の何割がスナイパーなのかは不明です。オーブの数から推測すると、約1割になるので、確率的には綺麗に収束しているな、と。
最後に、あの賽銭箱(オートエントリーユニット)についてなんだけど、ステチャレ時のレベルアップチャンスで一時期多用していたことがあって、3000枚×54=162000枚のメダルを投入していたことが発覚しました。
・・・というわけで、およそ2年間におよぶ最終成績でした。このゲームって自分は完全な物理抽選ではないと思っているんだけど、こうやって数字を眺めてみると、そこまで確率は大きく逸脱していないというか、というか、むしろ完全物理抽選よりも勝率が少しだけ上がるように機械がさりげなくコントロールしている感じがあるな、というのが感想です。
本当に、ゲームバランスがよくできた作品でした。FT4はジャックポット枚数のインフレがすっごい気になるから、本音ではFT3のままでいて欲しいんだけど、これも時代の流れ・・・受け入れるしかない!(どっかでFT3やれるとこねーかな)
追記:イベントカレンダー見ると、なんか4月までFT3動かす気マンマンっぽいぞ。まさかの4への移行見送りか!??