参考文献:全国大学書道学会編『書の古典と理論』
仮名の成立と書風の変遷
今度は日本の書道史。
弥生時代
日本の書の歴史は、大陸からの漢字伝来に始まるが、その伝来の痕跡はわずかに残された金石文(金属や石に刻印された文章のこと)や木簡に限られる。
『貨泉』(青銅製の貨幣)と『金印』は日本への漢字伝来を示す最古の出土品である。
古墳時代
『石上神宮七支刀銘』や『隅田八幡宮神社人物画象鏡銘』などの金石文には、すでに漢字の音を借りて日本語を表記する万葉仮名的な使用例が見られ、国文学や書道史の上で重要な資料となっている。
稲荷山古墳の鉄剣に記された銘文は、線が細く太さも均質でネームペンで書いたような可愛い古朴な書体である。
飛鳥時代
『法隆寺金堂釈迦造像銘』に見事な中国南北朝の文字が見られる。この格調高い書風の広がりは、聖徳太子直筆と言われる『法華義疏(ほっけぎしょ)』にも見られる。『法華義疏』の書体は、横に潰れた漢隷の流れを組み、さらにそれを行書的に崩したような印象を与えるものである。
しかし、飛鳥時代には、これらの書体とは別に、非常に洗練された楷書である『金剛場陀羅尼経(こんごうじょうだらにきょう)』など、隋風書風も見え始め、飛鳥時代の書道は、この二つの影響下に置かれていた。
奈良時代
仏教の興隆によって写経が国家的事業になり、数々の名筆が生まれた。
その白眉といわれる国分寺経の『金光明最勝王経』は、潤いを帯びた線質、唐経には見られない筆致を醸している。
写経の誤字脱字には罰金があったらしく、一行17字詰めの厳正な楷書は筆力に溢れ、隙がなく、やや扁平な字形が特徴である。
写経以外では、知識階級の日常の書体や書風を伺える、正倉院文書と木簡を忘れてはならない。光明皇后の『楽毅論』は、唐代に流行した王羲之の書を臨書したものである。
木簡では習字木簡や万葉仮名木簡が各地で発掘されており、公文書の記録は漢文、また和文でも男手(万葉仮名の楷書)だったことがわかる。
この男手は早書きされていくうちに、やがて草書体の草がなに発展する。草仮名は時間短縮のために、字と字をつなげるといった工夫(連綿)が見られ、その結果である繊細な線質は、筆の流れの美しさを表現する芸術的な技法にもなった。
平安時代
日本書道の確立期にあたり、その基本的書風は現代に根強く生きている。
また、漢字の草書を極度に省略化した仮名という独自の書体が生まれた。
ただし遣唐使の派遣が中止されるまでは、引き続いて中国の書法が継承された。その頂点には、嵯峨天皇、空海、橘逸勢の三筆が君臨し、王羲之を主流とした伝統的書風の中に温雅な風韻をかもした。
嵯峨天皇が、最長の弟子の光定が比叡山の戒壇の設立に奔走したことを讃え、したためた書である『光定戒牒』は、字によって線の太さ、墨の乾湿を意図的に変化させており、「為」などの向勢(縦線が互いに膨らみ合うこと)と、「立」などの背勢(縦線が互いに反ること)の見事な調和が取られている。
そんな嵯峨天皇が、唐人の手によるものだと勘違いし、書の腕前に脱帽したのが空海である。
空海が、当時はまだ仲が良かった最澄に宛てた手紙である『風信帖(ふうしんじょう)』は、重厚で落ち着きがある王羲之の書法をよく学んだ上で、充分に自己のものへと消化し、そこに日本的な情趣をも醸し出している。収筆を上に跳ね上げることで、筆の流れにスピード感を感じさせている。
橘逸勢(たちばなのはやなり)は、筆の性能を活かしきり、自由奔放でありながら格調高い書をしたためた。そこには緩急抑揚のついた強い筆力と躍動感が感じられる。
やがて三跡(小野道風、藤原佐理、藤原行成)の時代になると、小野道風が和様の滑らかな線質で唐風の鋭利な感触を払拭し、仮名の隆盛とともに日本書道独自の流麗な筆運びのきっかけを作った。
ついで藤原行成が道風を範とし、穏やかな線に緩急の速度と抑揚を加え、和様の姿を確立させた。彼の書は、「世尊寺流」と呼ばれ、曲麗優雅な宮廷文化を代表する名跡を残した。
また、清少納言とも親交があった行成は『関戸本古今和歌集』を、リズミカルで生きの長い連綿の女手で書いており、この時代は、紫式部が『源氏物語』を、清少納言が『枕草子』を著す、女手の黄金時代であった。
平安時代末期になると、従来の艶かしい美から転じて、個性的な書風が見え始め、仮名の完成美を示した。特に10世紀中頃から、書写の速度やリズムに種々の変容が現れて、能書家では、行成の孫の藤原伊房(これふさ)が、鋭さと速さ、秀麗にして気迫に満ちたユニークな書風を残している。
鎌倉時代
まず、藤原俊成と定家父子が活躍した。
藤原定家の書風は、父俊成の角張って鋭い書風と異なり、扁平な字形が多く、筆圧の強弱も極端で、ふにゃふにゃ、総じてくせの強いものであったが(自身も悪筆と認めていた)、当時の歌学の権威でもあったため、そのくせは個性と捉えられ、大いに尊ばれ、後世は定家流と呼ばれて広がった。
また、著名な歌人である西行にも魅力ある書風が見られるなど、個性的な書が書かれた一方で、画一的な亜流が生じたのも、この時代の特徴である。
一方、平安時代末期からの日宋貿易で、禅宗とともに新しい宋風の書が輸入され、これは禅宗様と呼ばれた。
室町時代
書道史的には見るべきものは多くない。明からの影響も乏しく、型にはまった保守的傾向の強い書風が多く見られた。
その中でも一休宗純は、筆を紙面にこすりつけるような鋭く激しい特異な筆勢と、大胆にディフォルメされた奔放な書風で気を吐いた。
安土桃山時代
室町時代の沈滞した空気を排除し、新風が吹き込まれた。
後陽成天皇は雄大な書風を見せた。
公家の近衛信尹は大字のかなに異色の書風を見せた。
江戸時代
初期に大陸からやってきた禅宗の黄檗僧(おうばくそう)たちが中国明代の書をもたらした。彼らの雄渾な筆致の新書法は、やがて唐様と呼ばれ大いに広まった。
江戸中期には近衛家煕によって、平安時代のかなに光が当てられた。
この時代の一般庶民の文字教育は、特に目立った能書家がいない草書の御家流が幕府公認の書体に規定されていたため、実用を旨にして形式化、低俗化の一途をたどった。しかし識字率の向上には一定の役割を果たした。
明治時代以降
明治時代以降、文学作品の多くが、漢字仮名交じりの表記による口語文で書かれるようになった。一方、書道の作品では、漢詩や漢文、和歌や俳句を、伝統的な手法によって表現する作品が主流を占め続けていた。
その後、昭和に入ると、漢字仮名交じりで書かれた同時代の文学作品を新たな書表現で作品化しようという動きが生まれる。
戦後、1954年に毎日書道展で近代詩部門が設けられると、翌年には日展の書の部門において調和体と称する漢字仮名交じり作品の出展区分が設けられた。
また、従来は小さく書かれ、展覧会の片隅の机に並べられるという地味なイメージがあったかなの書を、屏風、軸、額にして絵画作品のように壁に飾って鑑賞するという、大字かな運動が全国的に展開された。
書道覚え書き①
2017-08-08 18:53:20 (8 years ago)
参考文献:全国大学書道学会編『書の古典と理論』
漢字の成立と書体の変化
字が恐ろしく下手な私には異世界の単位。文字が綺麗ってだけで、なんか育ちが良さそうに見えるもんな。前にも書いたかもしれなけど、個人的には筆圧が強い人は、筋肉や神経でちゃんと腕の動きを制御していて、上手な字が書けるイメージがある。
私なんて非力だから、ボーリングのように腕を持ってかれて、たいていの横棒は勢いを失って下にさがっていく。筆跡鑑定が宇宙一容易な男だという自負があります。
新石器時代(紀元前1万年~)
新石器時代に広く用いられた陶製の容器には、符号や略号、図象の類が描かれていた。これは陶文または刻画符号と呼ばれる。
殷~周時代(紀元前17世紀~紀元前3世紀)
現在最も古いとされる漢字は殷(商)時代の甲骨文である。
甲骨文とは、亀の甲羅や獣の骨などに刻まれた文字で、鋭利な小刀で刻むことから契文とも言い、また文章の内容がト占(相手に何かを選ばせて占うタイプの占い。タロットやおみくじなど)に関することから卜辞(ぼくじ)とも言う。
甲骨文の発見は、19世紀末に王懿栄(おういえい)と劉鶚(りゅうがく)が薬局から買った龍骨に符号らしきものを見つけたことによる。現在では相当数の文字が解読され、当時すでに厳密な文字体系を備えていたことがわかる。
甲骨文字の線は単調な直線で、文字というよりは記号や絵に近い様相のものが多い。
殷・周は青銅器の時代である。
青銅器でできた釣鐘状の楽器(鐘しょう)や食器の(鼎てい)に施された文字は金文(鐘鼎文字)と呼ばれる。
殷中期の遺跡から出土された青銅器からすでに銘文(金属や石に刻まれた文章のこと)と思しきものが現れている。これらの文字は、溶けた金属を鋳型に流し込み、鋳込まれて制作された。
周の時代になると、祭祀に使われた青銅器が王の権威を示すものに変わり、文字の書風は整って装飾性と多様性が強くなった。
書写材料は、甲骨、金属だけではなく、石、玉、竹木など様々なものが用いられた。また、殷の時代で、すでに筆が使用されていたことが分かっている。
書体は、縦に長く書かれ、文字の大きさにも変化がつけられるようになった。
また、細く単調で直線的だった線も、太さに変化がつき、曲線を多用している。しかし、甲骨文字同様、線の先が尖っているものが多い。
春秋時代~戦国時代(紀元前8世紀~紀元前3世紀)
戦国時代になると金文にあった象形文字のテイストは薄れ、左右相称の整った字形となった。篆字体の原型とされる。
書体は多様化し、複雑な書体の籀文(ちゅうぶん)と、簡略化された書体の古文との差別化も進んだ。
秦~漢時代(紀元前8世紀~3世紀)
周の封建制度に対し、秦は中央集権体制を樹立し、その一環として文字の統一が試みられた。これにより文書行政が施行され、小篆が公式書体として用いられるようになった。
小篆は、線が水平・垂直で、等分割の荘厳な趣が特徴である。文字は左右対称でやや縦長、線の太さは均一であった。
日常の記録には、篆書が簡略化され実用的なものになった隷書(秦隷)が用いられた。これを隷変という。
その特徴は、カーブを尖らせる、曲線を直線に変える、線を連続させる、筆画を短くしたり省いたりする、よく似た複雑な形をひとつの符号で代表させまとめる、などである。
こういった簡略化は当時の文書行政の広がりと無縁ではなかった。
前漢時代になると、毛筆が発達し、これに適した隷書は、次第に準公用体として認められるようになり、他の書体を駆逐するまでに広まった。
楷書・行書や草書は、すべてこの隷書が発展したものであると考えられている。
この時代の隷書には、横線や右払いの終わりにつける三角形のうろこである波磔(はたく)が芽生え、線の抑揚と筆の穂先の意図的な開閉が見られる。
後漢時代になると横に潰れた字体、上下左右等間隔の字の並びなどが特徴である漢隷(八分)が確立した。
小篆は印鑑という特殊な用途にのみ使われるようになった(篆刻)。
三国~西晋時代(3~4世紀)
後漢が滅亡すると、魏・呉・蜀の三つの国が天下を三分した。
この時代の特徴は、曹操によって立碑が禁止されたことで墓に納める墓誌が制作されるようになったこと、楷書(隷書)が定式化したこと、字を巧みに書く芸術である能書が出現したことなどが挙げられる。
北魏の楷書の名品とされる『張猛龍碑』では、字体が左下がり(右上がり)で、不等分割、点描の疎密に工夫が見られる。線は強靭で絶妙な均衡美が表現されている。
東晋時代(4~5世紀)
五胡の乱によって西晋が滅ぼされ、不安定な政治情勢の中、竹林の七賢(道教的な思想のもとに儒教的倫理の束縛を嫌い自由気ままに生きた賢者のこと)を理想とする貴族文化が花開いた。
能書家の王羲之(おうぎし)は、より洗練された芸術性の高い書を残し、後世書聖と称えられた。しかし、王羲之本人の書はひとつも現存せず、残っているのは全て臨書である。
王羲之の『喪乱帖』は筆運びのリズムが心地よく、字によって線の太さを変えメリハリをつけている。左右への振れ幅も大きく、字の上部と下部における重心の移動など、躍動的である。
王羲之の子の王献之(おうけんし)も能書として知られ、父と共に書の二王とされた。
南北朝時代(5~6世紀)
南朝では、豊かな経済力を背景に文学や芸術論が盛んになっただけでなく、仏教も栄えた。
北朝では、北魏の孝文帝が南朝文化の摂取に努めたが、とりわけ仏教関係の石窟造営が盛んに行われた。代表的な龍門石窟に記された『造像記』は方筆を主とする龍門様式の筆法である。
隋~唐時代(6~10世紀)
隋時代の書は、南北朝から唐への過渡期に当たるものと言われている。
三過折(起筆→送筆→収筆の3段階で線を引くこと)を備えた方正な字形である楷書はかなり洗練され、唐を待たずすでに完成期に近づいていた。王羲之七代目の子孫である智永は、中学校の美術のレタリングの授業で習う永字八法の創始者である。
隋の禅譲を受けて、統一王朝の唐ができると、大宗が宮中に弘文館を設立し文武官に書を学ばせた。大宗は王羲之の書を愛好し、また自身も書をたしなみ、行書の『晋祠銘』や『温泉銘』を残している。
草書(行書をさらに崩した筆記体のような字体。形を覚えないともはや読めない)では、則天武后が書いた『昇仙太子碑』などがある。
中唐の玄宗の治世には最も文化が爛熟し、文学では李白、杜甫が出た。
書では、張旭(ちょうきょく)、懐素(かいそ)が登場し、自由奔放な草書(狂草)が書かれた。
楷書は形骸化した。
宋~元時代(10~14世紀)
形骸化した唐代の書に対して、宋代では個人の精神性を尊重した。
蘇軾(そしょく)、黄庭堅(こうていけん)、米芾(べいふつ)、蔡襄(さいじょう)は宋の四大家と呼ばれる。
元時代になると趙孟頫(ちょうもうふ)が王羲之をリスペクトし、鮮于枢(せんうすう)とともに併称され、後半にはトルコ系の康里巙巙(こうりきき)が登場し、章草(隷書と草書のちょうど間の字体)を得意とした。
明~清時代(14~20世紀)
製墨技術が最高潮に達した時代。
明末期の書家は、連綿(つなげ字)を多用した行書体を追求し、特に長条幅(長い掛け軸状の半紙に書く)という新しい表現形式を生んだ。
清代前期は、名跡の模本や法帖を学ぶ帖学派の時代とされている。
清代末期は、趙之謙(ちょうしけん)や呉昌碩(ごしょうせき)のように、詩、書、画、篆刻をよくして独自の境地を築いた文人が輩出し、日本にも影響を与えている。
また1880年に来日した楊守敬(ようしゅけい)は北碑の書法を伝え、これにより日本の近代書道が始まった。
漢字の成立と書体の変化
字が恐ろしく下手な私には異世界の単位。文字が綺麗ってだけで、なんか育ちが良さそうに見えるもんな。前にも書いたかもしれなけど、個人的には筆圧が強い人は、筋肉や神経でちゃんと腕の動きを制御していて、上手な字が書けるイメージがある。
私なんて非力だから、ボーリングのように腕を持ってかれて、たいていの横棒は勢いを失って下にさがっていく。筆跡鑑定が宇宙一容易な男だという自負があります。
新石器時代(紀元前1万年~)
新石器時代に広く用いられた陶製の容器には、符号や略号、図象の類が描かれていた。これは陶文または刻画符号と呼ばれる。
殷~周時代(紀元前17世紀~紀元前3世紀)
現在最も古いとされる漢字は殷(商)時代の甲骨文である。
甲骨文とは、亀の甲羅や獣の骨などに刻まれた文字で、鋭利な小刀で刻むことから契文とも言い、また文章の内容がト占(相手に何かを選ばせて占うタイプの占い。タロットやおみくじなど)に関することから卜辞(ぼくじ)とも言う。
甲骨文の発見は、19世紀末に王懿栄(おういえい)と劉鶚(りゅうがく)が薬局から買った龍骨に符号らしきものを見つけたことによる。現在では相当数の文字が解読され、当時すでに厳密な文字体系を備えていたことがわかる。
甲骨文字の線は単調な直線で、文字というよりは記号や絵に近い様相のものが多い。
殷・周は青銅器の時代である。
青銅器でできた釣鐘状の楽器(鐘しょう)や食器の(鼎てい)に施された文字は金文(鐘鼎文字)と呼ばれる。
殷中期の遺跡から出土された青銅器からすでに銘文(金属や石に刻まれた文章のこと)と思しきものが現れている。これらの文字は、溶けた金属を鋳型に流し込み、鋳込まれて制作された。
周の時代になると、祭祀に使われた青銅器が王の権威を示すものに変わり、文字の書風は整って装飾性と多様性が強くなった。
書写材料は、甲骨、金属だけではなく、石、玉、竹木など様々なものが用いられた。また、殷の時代で、すでに筆が使用されていたことが分かっている。
書体は、縦に長く書かれ、文字の大きさにも変化がつけられるようになった。
また、細く単調で直線的だった線も、太さに変化がつき、曲線を多用している。しかし、甲骨文字同様、線の先が尖っているものが多い。
春秋時代~戦国時代(紀元前8世紀~紀元前3世紀)
戦国時代になると金文にあった象形文字のテイストは薄れ、左右相称の整った字形となった。篆字体の原型とされる。
書体は多様化し、複雑な書体の籀文(ちゅうぶん)と、簡略化された書体の古文との差別化も進んだ。
秦~漢時代(紀元前8世紀~3世紀)
周の封建制度に対し、秦は中央集権体制を樹立し、その一環として文字の統一が試みられた。これにより文書行政が施行され、小篆が公式書体として用いられるようになった。
小篆は、線が水平・垂直で、等分割の荘厳な趣が特徴である。文字は左右対称でやや縦長、線の太さは均一であった。
日常の記録には、篆書が簡略化され実用的なものになった隷書(秦隷)が用いられた。これを隷変という。
その特徴は、カーブを尖らせる、曲線を直線に変える、線を連続させる、筆画を短くしたり省いたりする、よく似た複雑な形をひとつの符号で代表させまとめる、などである。
こういった簡略化は当時の文書行政の広がりと無縁ではなかった。
前漢時代になると、毛筆が発達し、これに適した隷書は、次第に準公用体として認められるようになり、他の書体を駆逐するまでに広まった。
楷書・行書や草書は、すべてこの隷書が発展したものであると考えられている。
この時代の隷書には、横線や右払いの終わりにつける三角形のうろこである波磔(はたく)が芽生え、線の抑揚と筆の穂先の意図的な開閉が見られる。
後漢時代になると横に潰れた字体、上下左右等間隔の字の並びなどが特徴である漢隷(八分)が確立した。
小篆は印鑑という特殊な用途にのみ使われるようになった(篆刻)。
三国~西晋時代(3~4世紀)
後漢が滅亡すると、魏・呉・蜀の三つの国が天下を三分した。
この時代の特徴は、曹操によって立碑が禁止されたことで墓に納める墓誌が制作されるようになったこと、楷書(隷書)が定式化したこと、字を巧みに書く芸術である能書が出現したことなどが挙げられる。
北魏の楷書の名品とされる『張猛龍碑』では、字体が左下がり(右上がり)で、不等分割、点描の疎密に工夫が見られる。線は強靭で絶妙な均衡美が表現されている。
東晋時代(4~5世紀)
五胡の乱によって西晋が滅ぼされ、不安定な政治情勢の中、竹林の七賢(道教的な思想のもとに儒教的倫理の束縛を嫌い自由気ままに生きた賢者のこと)を理想とする貴族文化が花開いた。
能書家の王羲之(おうぎし)は、より洗練された芸術性の高い書を残し、後世書聖と称えられた。しかし、王羲之本人の書はひとつも現存せず、残っているのは全て臨書である。
王羲之の『喪乱帖』は筆運びのリズムが心地よく、字によって線の太さを変えメリハリをつけている。左右への振れ幅も大きく、字の上部と下部における重心の移動など、躍動的である。
王羲之の子の王献之(おうけんし)も能書として知られ、父と共に書の二王とされた。
南北朝時代(5~6世紀)
南朝では、豊かな経済力を背景に文学や芸術論が盛んになっただけでなく、仏教も栄えた。
北朝では、北魏の孝文帝が南朝文化の摂取に努めたが、とりわけ仏教関係の石窟造営が盛んに行われた。代表的な龍門石窟に記された『造像記』は方筆を主とする龍門様式の筆法である。
隋~唐時代(6~10世紀)
隋時代の書は、南北朝から唐への過渡期に当たるものと言われている。
三過折(起筆→送筆→収筆の3段階で線を引くこと)を備えた方正な字形である楷書はかなり洗練され、唐を待たずすでに完成期に近づいていた。王羲之七代目の子孫である智永は、中学校の美術のレタリングの授業で習う永字八法の創始者である。
隋の禅譲を受けて、統一王朝の唐ができると、大宗が宮中に弘文館を設立し文武官に書を学ばせた。大宗は王羲之の書を愛好し、また自身も書をたしなみ、行書の『晋祠銘』や『温泉銘』を残している。
草書(行書をさらに崩した筆記体のような字体。形を覚えないともはや読めない)では、則天武后が書いた『昇仙太子碑』などがある。
中唐の玄宗の治世には最も文化が爛熟し、文学では李白、杜甫が出た。
書では、張旭(ちょうきょく)、懐素(かいそ)が登場し、自由奔放な草書(狂草)が書かれた。
楷書は形骸化した。
宋~元時代(10~14世紀)
形骸化した唐代の書に対して、宋代では個人の精神性を尊重した。
蘇軾(そしょく)、黄庭堅(こうていけん)、米芾(べいふつ)、蔡襄(さいじょう)は宋の四大家と呼ばれる。
元時代になると趙孟頫(ちょうもうふ)が王羲之をリスペクトし、鮮于枢(せんうすう)とともに併称され、後半にはトルコ系の康里巙巙(こうりきき)が登場し、章草(隷書と草書のちょうど間の字体)を得意とした。
明~清時代(14~20世紀)
製墨技術が最高潮に達した時代。
明末期の書家は、連綿(つなげ字)を多用した行書体を追求し、特に長条幅(長い掛け軸状の半紙に書く)という新しい表現形式を生んだ。
清代前期は、名跡の模本や法帖を学ぶ帖学派の時代とされている。
清代末期は、趙之謙(ちょうしけん)や呉昌碩(ごしょうせき)のように、詩、書、画、篆刻をよくして独自の境地を築いた文人が輩出し、日本にも影響を与えている。
また1880年に来日した楊守敬(ようしゅけい)は北碑の書法を伝え、これにより日本の近代書道が始まった。
ギガ恐竜博への旅(もふカフェ付き)
2017-08-08 11:06:27 (8 years ago)
ここのところ再び毎年恒例になった感がある幕張メッセのイベント。スクーリングの帰りにコシサウルスさんと行ってきました。こしさんも相変わらず向学心旺盛で、なぜか発達心理学のピアジェとか学んでいるし、さらに政治ツイートをうそぶく人が誰も読んでくれない、政治学を基礎からしっかり学べ、不毛なやりとりを70%位カットできる本『補正版政治学』にも手を出してくれて、やっぱり学術系の本を読む人との会話は楽しいよなっていう。学歴あっても読まない人は読まないもんな。
で、恐竜博の内容なんだけど、まあなんちゃらサウルスっていう(名前を覚えるのすら諦めた)、中国で割とよくいるタイプのでかマメンチ系の恐竜がメインで、あとはまあ一通りの恐竜のグループが網羅されててすごいんだけど、そのほとんどが福井県立恐竜博物館収蔵品で、福井県の幕張巡業みたかったというw
あと、会場はいつものホール11で広さは一緒なんだけど、こしさんなんかは狭く感じたとか言ってて、それは多分、順路が今年はグネグネしてなくて、でかマメンチの周りをシンプルに一周するような感じだったから、会場の全体像がかなり早い段階で分かっちゃって、それで短く感じだのだろうと思われる。こういう感覚って面白いよね。空間の使い方っていうか。

でかマメンチ系のギガ恐竜。

バックショット。でかい。

陸上の人まで襲ってしまうアーウィーソウトルとは、いったいどんな怪物なのだろうか・・・(パキPさんにしかわからないネタ)
ピースケがいじめられてるよ!(マロさんしかわからないネタ)

こしさんいわく、首長竜の手脚の付け根はウミガメのようにかなり骨の位置関係が変わっちゃっていて、発生学的も面白いらしい。熱弁してくれたんだけど、メモ持ってなかったから詳細は忘れた(^_^;)しかし深海魚みたいなすごい牙だな。

プテラノドン。翼竜の顔として不動の地位を築いているだけあってすごい優美でかっこいい。しかしジュラシックワールドの翼竜はダサかったな。どうにかならなかったのかよ。ロストワールドジュラシックパークの使い回しで十分かっこいいのによ。

近年の分子分類に基づく大胆な人事異動により、カミナリ竜の部署に一人左遷させられ話題となっているヘレラサウルス。これはあとでイラストを描きたい。確かにプラテオサウルスとかに近いようにも・・・見え・・・

ない。

この前たまたまイラストを描き直していたコンカベナトール。いい答え合わせになった。けっこう再現できたな。

それとは逆に、イラストを描いているときはもっと大きい生き物だと思っていた福井べナトール。こんなにちっちゃいとは!!ベロキラプトルとサイズも変わらないわけね。でもポーズはだいたい一緒にしたし、顎の反ってるところとかうまく再現できたと思う。上顎と下顎で剃り方が逆で、口を閉じたとき隙間が出来そうなのがポイント。

ただ、これはトロオドンとかもそうだった気がするけど、目の穴がスポーツカーのガルウィングみたいに上の方まで空いてて、目がどうやって入ってたのかすごい気になる。案外ジュラシックパークTHEゲームのトロオドンみたいに頭頂部を向いていたのかもしれない。

今、ちょっと描き直しているのがステゴサウルスなんだけど、本当にこの恐竜が一番へんてこっていうか、現生動物にお手本がいなくて大変。だいたいあの板が背骨に沿う形で並んでいるのがすごい。胴体は、まあ構造上くねらせられなかっただろうからいいけど、首と尻尾はあの板が邪魔でほとんど曲げられない気がするんだけど。
こしさんにそれを言ったら、あの板は骨だからあの板自体がしなるっていうのは無理なので、意外と板は体にしっかりくっついてなかったんじゃないかとか言ってて、じゃあわりと頻繁に取れたんかなっていう。で、取れたら取れたで再生するのか、みたいな、新たな謎が生まれた。

それとステゴサウルスって、くちばしの先が尖っているイメージがあって、そういう復元が多いんだけど、よくみるとカモみたいになってて口の先とがってない!
さっそく描き直したよwこれはトゥオジャンゴとかヘスペロもそうで、剣竜に共通するっぽい。
あと、幕張に数年前現れたギガAEONのモフモフカフェにも寄ってきた。つーか、この施設、自分が幕張に住んでた時にはなくて、噂には聞いていたが本当にギガ。南船橋の巨大モールのららぽーとが噛ませ犬になっちゃうくらいでかい。
ほいで、入場料払えばクリーチャーどもを触り放題なんだけど、こんなアニマルワールドの中で飲食をする勇気が私にはなかった(^_^;)コーヒーに上から尿酸投下されそうじゃん。

モフモフ。可愛い。仰向けにして足を伸ばすとヒヨコは寝ちゃうらしいが、それは胸骨が肺を圧迫して落ちてんじゃないかという説もある(じゃ、ダメじゃん!)

フトアゴヒゲトカゲ。あまりモフモフじゃないが、顔の幅が広くおめめが丸く、総じてベビーフェイスで結構可愛い。
初めて触ったけど、アンキロサウルスのようなこの脇腹のトゲトゲ、すごい見掛け倒しでゴムみたいに柔らかい。背中が多少逆なでするとざらつくけど、想像以上に皮膚が薄い。触ってみるもんだ。

名前忘れた。ヒョウモントカゲモドキだっけかな。トカゲモドキの割に本家のトカゲ同様に尻尾を自切する。すごい触り心地がいい。しかし結局のところヤモリに過ぎない。

グリーンイグアナ。脚が長くすごい活動的。目をつむって穏やかな表情だが、こしさんによれば爬虫類や鳥類はイラつているときに目をつむるらしい。ダメじゃん!
あと、あたり構わずついばんでくる凶暴なコンゴウインコ(目がイっちゃってる)や、シューシュー唸って穏やかじゃないメンフクロウとかいろいろヤバそうな奴らがいました。こんな狭いところに閉じ込められ、人間どもの好奇の目で見つめられさぞストレスなのだろう。
フクロウって昨今はフクロウカフェとかフクロウ女子とかで人になつくかわいいペットなのかなってイメージあったけど、とどのつまりプレデター。オレの目の前に立つな的に、目の前のものは攻撃対象にしてくるぞ。全然なつかねーよw
で、恐竜博の内容なんだけど、まあなんちゃらサウルスっていう(名前を覚えるのすら諦めた)、中国で割とよくいるタイプのでかマメンチ系の恐竜がメインで、あとはまあ一通りの恐竜のグループが網羅されててすごいんだけど、そのほとんどが福井県立恐竜博物館収蔵品で、福井県の幕張巡業みたかったというw
あと、会場はいつものホール11で広さは一緒なんだけど、こしさんなんかは狭く感じたとか言ってて、それは多分、順路が今年はグネグネしてなくて、でかマメンチの周りをシンプルに一周するような感じだったから、会場の全体像がかなり早い段階で分かっちゃって、それで短く感じだのだろうと思われる。こういう感覚って面白いよね。空間の使い方っていうか。

でかマメンチ系のギガ恐竜。

バックショット。でかい。

陸上の人まで襲ってしまうアーウィーソウトルとは、いったいどんな怪物なのだろうか・・・(パキPさんにしかわからないネタ)
ピースケがいじめられてるよ!(マロさんしかわからないネタ)

こしさんいわく、首長竜の手脚の付け根はウミガメのようにかなり骨の位置関係が変わっちゃっていて、発生学的も面白いらしい。熱弁してくれたんだけど、メモ持ってなかったから詳細は忘れた(^_^;)しかし深海魚みたいなすごい牙だな。

プテラノドン。翼竜の顔として不動の地位を築いているだけあってすごい優美でかっこいい。しかしジュラシックワールドの翼竜はダサかったな。どうにかならなかったのかよ。ロストワールドジュラシックパークの使い回しで十分かっこいいのによ。

近年の分子分類に基づく大胆な人事異動により、カミナリ竜の部署に一人左遷させられ話題となっているヘレラサウルス。これはあとでイラストを描きたい。確かにプラテオサウルスとかに近いようにも・・・見え・・・

ない。

この前たまたまイラストを描き直していたコンカベナトール。いい答え合わせになった。けっこう再現できたな。

それとは逆に、イラストを描いているときはもっと大きい生き物だと思っていた福井べナトール。こんなにちっちゃいとは!!ベロキラプトルとサイズも変わらないわけね。でもポーズはだいたい一緒にしたし、顎の反ってるところとかうまく再現できたと思う。上顎と下顎で剃り方が逆で、口を閉じたとき隙間が出来そうなのがポイント。

ただ、これはトロオドンとかもそうだった気がするけど、目の穴がスポーツカーのガルウィングみたいに上の方まで空いてて、目がどうやって入ってたのかすごい気になる。案外ジュラシックパークTHEゲームのトロオドンみたいに頭頂部を向いていたのかもしれない。

今、ちょっと描き直しているのがステゴサウルスなんだけど、本当にこの恐竜が一番へんてこっていうか、現生動物にお手本がいなくて大変。だいたいあの板が背骨に沿う形で並んでいるのがすごい。胴体は、まあ構造上くねらせられなかっただろうからいいけど、首と尻尾はあの板が邪魔でほとんど曲げられない気がするんだけど。
こしさんにそれを言ったら、あの板は骨だからあの板自体がしなるっていうのは無理なので、意外と板は体にしっかりくっついてなかったんじゃないかとか言ってて、じゃあわりと頻繁に取れたんかなっていう。で、取れたら取れたで再生するのか、みたいな、新たな謎が生まれた。

それとステゴサウルスって、くちばしの先が尖っているイメージがあって、そういう復元が多いんだけど、よくみるとカモみたいになってて口の先とがってない!
さっそく描き直したよwこれはトゥオジャンゴとかヘスペロもそうで、剣竜に共通するっぽい。
あと、幕張に数年前現れたギガAEONのモフモフカフェにも寄ってきた。つーか、この施設、自分が幕張に住んでた時にはなくて、噂には聞いていたが本当にギガ。南船橋の巨大モールのららぽーとが噛ませ犬になっちゃうくらいでかい。
ほいで、入場料払えばクリーチャーどもを触り放題なんだけど、こんなアニマルワールドの中で飲食をする勇気が私にはなかった(^_^;)コーヒーに上から尿酸投下されそうじゃん。

モフモフ。可愛い。仰向けにして足を伸ばすとヒヨコは寝ちゃうらしいが、それは胸骨が肺を圧迫して落ちてんじゃないかという説もある(じゃ、ダメじゃん!)

フトアゴヒゲトカゲ。あまりモフモフじゃないが、顔の幅が広くおめめが丸く、総じてベビーフェイスで結構可愛い。
初めて触ったけど、アンキロサウルスのようなこの脇腹のトゲトゲ、すごい見掛け倒しでゴムみたいに柔らかい。背中が多少逆なでするとざらつくけど、想像以上に皮膚が薄い。触ってみるもんだ。

名前忘れた。ヒョウモントカゲモドキだっけかな。トカゲモドキの割に本家のトカゲ同様に尻尾を自切する。すごい触り心地がいい。しかし結局のところヤモリに過ぎない。

グリーンイグアナ。脚が長くすごい活動的。目をつむって穏やかな表情だが、こしさんによれば爬虫類や鳥類はイラつているときに目をつむるらしい。ダメじゃん!
あと、あたり構わずついばんでくる凶暴なコンゴウインコ(目がイっちゃってる)や、シューシュー唸って穏やかじゃないメンフクロウとかいろいろヤバそうな奴らがいました。こんな狭いところに閉じ込められ、人間どもの好奇の目で見つめられさぞストレスなのだろう。
フクロウって昨今はフクロウカフェとかフクロウ女子とかで人になつくかわいいペットなのかなってイメージあったけど、とどのつまりプレデター。オレの目の前に立つな的に、目の前のものは攻撃対象にしてくるぞ。全然なつかねーよw
コンピュータ演習覚え書き
2017-08-05 18:09:22 (8 years ago)
-
カテゴリタグ:
- 数学
終わった~~~!今までのスクーリングで一番辛かった~~!!一言で言って・・・
性に合わねえ!

サーバー。
そんなアナログ野郎の私にプログラミングなんていう高貴なものを教えれくれた先生は岡田斗司夫さんに激似(声および口調も激似)で、そのマニアックなオーラに期待満々だったんだけど・・・当然ながらそこで繰り広げられるのは、日本サブカル界に与えた機動戦士ガンダムの影響・・・なんかじゃなく、ひたすら地道にプログラム作成。
朝9時から夜6時までコンスタントに実技。コードを打っては、コンパイルし、バグをチェックし、ソースコードを修正し、コンパイルし・・・辛い。つーかこれを仕事にしているプログラマーとか頭おかしい。
耐えられん。耐えられんので、与えられた課題をさっさと終わらせてとっとと帰ろうと、三日分の課題を二日で終わらせ(出来は知らない)、とうとう開放された次第であります。
幸いなのは、オタキング・・・じゃなかった講義の先生がツンデレそうなところだね。あまりに初歩的なミスとか中学生レベルの計算間違いには「私は何度説明しましたか?聞いてましたよね?」「君は本当に数学の先生になるつもりなの?」と、厳しいんだけど、最終的には失笑して許しちゃうようなところあったもんな。つーか、この先生、なつかしの幾何学の先生だったんだな。お世話になりました。
コンピュータ演算三兄弟
ハードディスク(HDD):本棚。不揮発性記憶装置。
メモリ(RAM):本を広げる机(作業スペース)揮発性記憶装置(一時的に記憶)。
CPU:読む人の頭脳
理系なら必ず用いるたとえだが、内心わかるようなわからないようなである。
フォルダ
ファイルをしまう入れ物。昔はディレクトリと呼ばれていた。確かにそうだった!
カレントフォルダ
コマンドプロンプトで作業を行う特定のフォルダのこと。
TeX
読み方は「テフ」もしくは「テック」
スタンフォード大学の数学者ドナルド・クヌースによって40年以上前に作られた組版処理ソフトウェア(数学用ワープロ)。
クヌースが数学の本を出す際に、当時のタイプライターで打たれた数式が非常に見づらかったため、出版社とケンカ、もういいオレが作る!と開発された。
のちにプログラマーのレスリー・ランポートがこれを改良し(LaTeX)、さらに使いやすくなった。
数学者が作っただけあって、普通の文章を書くならワードに負ける気がするが、複雑な数式を手っ取り早く作るなら、こちらはかなり使いやすい。ただし、あになんぞ、我が人生で複雑な数式を書かんや(いやない)。
特徴としては、原稿(ソース)はテキストファイルなので汎用性が高い。
また、ワードと違いソースコードを打つので、それがどのように製版されるかはプログラミング中に確認できない(確認にはソースをコンパイルさせる必要がある)。
ちなみに、金儲けのために作ったわけではないというのがクヌースのモットーであるためフリーソフトです。
ソースコードの例
\documentclass[a4j,12pt]{jarticle}
\title{数学}
\author{多分ウィキペディア}
\date{2017年8月3日}
\begin{document}
\maketitle
広義には、超数学(メタ数学)などと呼ばれる枠組みにしたがって公理と推論規則が定められた体系一般を指す。現代的な数学においては、公理に定義される抽象的な構造を、形式論理を共通の枠組みとして用いて研究する。方法論の如何によらず最終的には、数学としての成果というものはほかの自然科学のように実験や観察によるものであってはならない。
\end{document}
※コードを書く際の注意
ソースの行の長さは適度に改行し短めにする。エラーの際には行単位でエラーが報告されるため、行が長いと探すのが面倒。
コメントアウト
%のあとに文章を書くと製版には反映されない、ソースコードの注釈(コメントアウト)となる。
基本設定
文字サイズ
[a4j,15pt]は、A4サイズの紙に12ポイント(ワードと違って12ポイントが最大!)の大きさで文字を表示させろという意味。かっこは[ ]を使う。
文字のサイズをもっと小さく、もしくは大きくする場合は
{\tiny }
{\scriptsize }
{\footnotesize }
{\small }
{\normalsize }
{\large }
{\Large }
{\LARGE }
{\huge }
{\Huge }
の順で大きくなる。
ノーマルサイズはドキュメントクラスの行で設定した文字サイズになり、それがサイズの基準になるので、12ptから10ptに変更するとtiny~Hugeもすべてそれにつられて若干小さくなる。
日付
\date{\today}と打つと自動的に今日の日付にしてくれる。
文体
{jarticle}は、ドキュメントのレイアウトを指定していてジャパンのアーティクルで和文の論文という意味。かっこは{ }を使う。
和文では自動的に段落の最初のマスは空欄にしてくれる。
スペース
LaTeXでは、複数の半角スペースをソースで入力しても、製版ではひとつ分しか空けてくれない。ただし全角スペースでは打った分だけ空白としてくれる。
ドキュメント内のテキストに、空白行を入れると製版では段落を変えてくれる。
\hspece{3cm}のようにスペースの長さを指定することもできる。
縦にスペースを空ける場合は\vspece{3cm}(バーティカルで縦)
強制改行
全角空欄+\\で強制改行(エンターキーの役割)。その場合、自動的に空欄は作られない。
書体変更
書体の変更はたとえば名前の部分だけローマン(rm)にしたいなら
\authior{TASHIRO{\rm TAKAHIRO}}
イタリック体なら
\authior{TASHIRO{\it TAKAHIRO}}
表・グラフ
|で地道に縦線を引く。横線は\hlineでひく。
|と|間にc(センターのc)を入れると線と線の間(セルの中)の文字は中央ぞろえ、l(レフト)だと左揃え、r(ライト)だと右揃えになる。
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\title{表組み}
\author{田代剛大}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
平成21年進路別中学校卒業者数
\begin{tabular}{|c||c|c|c|c|c|c|}\hline
& 高等学校等 & 専修学校 & 専修学校 & 公共職業能力 & & \\
都道府県名 & & (高等課程) & (一般課程)& 開発施設等 & 就職者 & 計\\
& 進学者 & 進学者 & 進学者 & 入学者数 & & \\
\hline \hline
埼玉 & 64,272 & 111 & 24 & 8 & 307 & 64,722\\
\hline
千葉 & 52,439 & 118 & 80 & 30 & 210 & 52,877\\
\hline
東京 & 98,537 & 388 & 242 & 53 & 448 & 99,668\\
\hline
神奈川 & 73,034 & 279 & 103 & 9 & 342 & 73,767 \\
\hline
新潟 & 23,301 & 2 & 4 & 13 & 43 & 23,363\\ \hline
\end{tabular}
\end{document}
数式
数式を書く場合は$と$の間にはさむと、数学の教科書のように表記してくれる。
$$と$$ではさむと、はさまれた数式は中央に並ぶ。
\timesで×のマーク。
\divで÷のマーク(ディヴィジョン)。
\frac{分子}{分母}で分数。
\sqrt2で2の平方根で√2。
^2で2乗
\leqで≦
\geqで≧
数式の通し番号をつけたい場合は\bigin{equation}と\end{equation}で複数の数式を挟むと自動的に式番号をつけてくれる。また、挟まれた部分は自動的に表記が数学になるので$$は不要で、つけるとエラーになる。
コード例:1
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\begin{document}
$$1,4,7,\ldots,22,25,\ldots$$
$$\sum_{k=1}^{n}(k^2+3k)$$
$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin x}{x}=1$$
$$S=\{(x,y)|1\leq x \leq 2,y\in R\}$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
\end{document}
コード例:2
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\begin{document}
\begin{eqnarray*}
\sqrt{15}\times\sqrt{10}
&=&\sqrt{5\times3}\times\sqrt{5\times2}\\
&=&\sqrt{5\times3\times5\times2}\\
&=&\sqrt{5^2\times3\times2}\\
&=&5\sqrt{6} \nonumber\\
\end{eqnarray*}
\begin{eqnarray*}
\frac{3x-y}{2}-\frac{x-4y}{4}&=&\frac{2(3x-y)}{4}-\frac{x-4y}{4}\\
&=&\frac{2(3x-y)-(x-4y)}{4}\\
&=&\frac{6x-2y-x+4y}{4}\\
&=&\frac{5x+2y}{4}
\end{eqnarray*}
%2ページ目
\newpage
\begin{flushleft}
$n$が奇数ならば、$n^2-1$は$8$で割り切れることを示せ。\\
\\
$n$を奇数とおくと$$n=2m^2+1$$($m$は自然数)となるので\\
\begin{eqnarray*}
(2m^2+1)^2-1
&=&4m^2+4m+1-1\\
&=&4m^2+4m\\
&=&4m(m+1)\\
\end{eqnarray*}
$m$と$m+1$は連続する自然数なので、どちらかは必ず偶数となり、その偶数に$4$がかけられるため、$n$が奇数ならば、$n^2-1$は$8$で割り切れる。\\
\end{flushleft}
%3ページ目
\newpage
\begin{flushleft}
$x=a^2+1$のとき\\
\\
$P=\sqrt{x+2a}+\sqrt{x-6a+8}$\\
\\
をaの多項式を用いて表せ。\\
\\
\\
$P=\sqrt{x+2a}+\sqrt{x-6a+8}$に$x=a^2+1$を代入すると\\
\\
$P=\sqrt{a^2+2a+1}+\sqrt{a^2-6a+9}$\\
\\
$\hspace{8mm}=\sqrt{(a+1)^2}+\sqrt{(a-3)^2}$\\
\\
$\hspace{8mm}=|a+1|+|a-3|$\\
\\
ここで場合分けを行うと\\
\\
$3\leq a$のとき\\
$P=a+1+a-3$\\
$\hspace{4mm}=2a-2$\\
\\
$-1 \leq a <3$のとき\\
$P=a+1-a+3$\\
$\hspace{4mm}=4$\\
\\
$a<-1$のとき\\
$P=-a-1-a+3$\\
$\hspace{4mm}=-2a+2$\\
\end{flushleft}
\end{document}
コード例:3
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\title{二次方程式の参考書}
\author{16PH5074 田代剛大}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{二次方程式の概要}
二次方程式は、以下のような最大次数が2である方程式である。\\
$$x^2=9$$ \\
$$4x^2=5$$ \\
$$x^2+8x+15=0$$ \\
特徴として、解が必ずしもひとつではなく、多くの場合二通りあるということや、解法が複数あり、どの解法が最も適しているかを、問題ごとに生徒自身が判断しなければならないこと、などが挙げられる。そのため、中学校の数学では難易度が高く、中学校三年生の一学期前半に因数分解や平方根を学習した上で、後半に取り上げられる。\\
\newpage
\section{二次方程式の解法}
二次方程式の解法を難易度順に紹介する。
\\
1.平方根の考え方を利用して解くタイプ\\
$(1) x^2=9$ \\
求める$x$は二乗して9になる数(9の平方根)と考えるので\\
\begin{eqnarray*}
x^2
&=&9\\
x
&=&\pm 3
\end{eqnarray*}
\\
$(2) x^2-3=0$ \\
このような場合は、移項したあとに根号を使う。\\
\begin{eqnarray*}
x^2-3
&=&0\\
x^2
&=&3\\
x
&=&\pm\sqrt3
\end{eqnarray*}
\\
$(3) (x+5)^2-3=0$ \\
( )の中の多項式をひとつの文字として考える。\\
\begin{eqnarray*}
(x+5)^2-3
&=&0\\
(x+5)^2
&=&3\\
x+5
&=&\pm\sqrt3\\
x
&=&-5\pm\sqrt3\\
\end{eqnarray*}
\newpage
\\
2.因数分解をして解くタイプ\\
$(1) x^2+x=0$ \\
各項の共通因数を見つけて( )でくくる。その後、( )の外側を0にする$x$の値、( )の内側を0にする$x$の値を考える。\\
\begin{eqnarray*}
x^2+x
&=&0\\
x(x+1)
&=&0\\
\end{eqnarray*}
$$x=0,x=-1$$\\
\\
$(2) x^2+8x+15=0$ \\
因数分解の公式を使う。足して8になり、かけて15になる、二つの数の組み合わせを考える。その後、左の( )の内側を0にする$x$の値、右の( )の内側を0にする$x$の値を考える。\\
\begin{eqnarray*}
x^2+8x+15
&=&0\\
(x+3)(x+5)
&=&0\\
\end{eqnarray*}
$$x=-3,x=-5$$\\
\\
$(3) x^2-12x+36=0$\\
これも因数分解の公式を使うが、解がひとつに定まるので注意する。\\
\begin{eqnarray*}
x^2-12x+36
&=&0\\
(x-6)(x-6)
&=&0\\
(x-6)^2
&=&0\\
\end{eqnarray*}
$$x=6$$\\
\\
3.完全平方式にして解くタイプ\\
因数分解ができない問題の場合、無理やり平方根の考え方で解けるように$( )^2$の形に表し直す方法。
まず、定数項を右辺に移項し、左辺を$( )^2$の形にするために必要な定数を両辺に加えて解く。
\begin{eqnarray*}
x^2-4x+2
&=&0\\
x^2-4x
&=&-2\\
x^2-4x+4
&=&-2+4\\
(x-2)^2
&=&2\\
x-2
&=&\pm\sqrt2\\
x
&=&2\pm\sqrt2\\
\end{eqnarray*}
\\
4.解の公式を用いて解くタイプ\\
完全平方をする解法を一般化したもの。
二次方程式$ax^2+bx+c=0$($a,b,c$は係数)を完全平方式にして解くと\\
\begin{eqnarray*}
ax^2+bx+c
&=&0\\
ax^2+bx
&=&-c\\
x^2+\frac{bx}{a}
&=&\frac{-c}{a}\\
(x+\frac{b}{2a})^2
&=&\frac{-c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}\\
(x+\frac{b}{2a})^2
&=&\frac{b^2-4ac}{4a^2}\\
x+\frac{b}{2a}
&=&\frac{\pm\sqrt{b^2 -4ac}}{2a}\\
x
&=&\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\\
\end{eqnarray*}
と、二次方程式の解の公式が得られる。この公式にそれぞれの係数$a,b,c$を代入すれば、混合が残る複雑な問題も短い時間で解くことができる。\\
完全平方式で解いたほうが早い問題もあるが、ひとつの判断基準として、$x$の係数が奇数で完全平方の際に分数になってしまう問題、$x^2$に係数がついていて全ての項を$x^2$の係数で等しく割る必要がある問題は、解の公式を使ったほうが早く解ける場合が多い。
\end{document}
・・・てな感じのことをやりました。これは地獄のほんの一部であることをお伝えしたい。

あと、今回は講義を受ける棟がいつもの理科の棟じゃなくて情報処理のエリアだったから、こんなところに海浜幕張的な空中庭園があるんだとか、けっこう前人未踏で

うお、こんなところには第二の学食が!
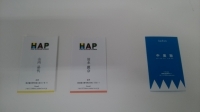
こっちではデザイン科の作品展がやってるぞ気をつけろ!
・・・みたいにひとりデザーテッドアイランドやってて楽しかった。でもプログラムは辛かった。数学は一種免許あきらめる。これを4回もやる根性が私にはない。プログラマーってそう考えると忍耐強いよな。確かに短気ですぐキレるイメージないもんな。
性に合わねえ!

サーバー。
そんなアナログ野郎の私にプログラミングなんていう高貴なものを教えれくれた先生は岡田斗司夫さんに激似(声および口調も激似)で、そのマニアックなオーラに期待満々だったんだけど・・・当然ながらそこで繰り広げられるのは、日本サブカル界に与えた機動戦士ガンダムの影響・・・なんかじゃなく、ひたすら地道にプログラム作成。
朝9時から夜6時までコンスタントに実技。コードを打っては、コンパイルし、バグをチェックし、ソースコードを修正し、コンパイルし・・・辛い。つーかこれを仕事にしているプログラマーとか頭おかしい。
耐えられん。耐えられんので、与えられた課題をさっさと終わらせてとっとと帰ろうと、三日分の課題を二日で終わらせ(出来は知らない)、とうとう開放された次第であります。
幸いなのは、オタキング・・・じゃなかった講義の先生がツンデレそうなところだね。あまりに初歩的なミスとか中学生レベルの計算間違いには「私は何度説明しましたか?聞いてましたよね?」「君は本当に数学の先生になるつもりなの?」と、厳しいんだけど、最終的には失笑して許しちゃうようなところあったもんな。つーか、この先生、なつかしの幾何学の先生だったんだな。お世話になりました。
コンピュータ演算三兄弟
ハードディスク(HDD):本棚。不揮発性記憶装置。
メモリ(RAM):本を広げる机(作業スペース)揮発性記憶装置(一時的に記憶)。
CPU:読む人の頭脳
理系なら必ず用いるたとえだが、内心わかるようなわからないようなである。
フォルダ
ファイルをしまう入れ物。昔はディレクトリと呼ばれていた。確かにそうだった!
カレントフォルダ
コマンドプロンプトで作業を行う特定のフォルダのこと。
TeX
読み方は「テフ」もしくは「テック」
スタンフォード大学の数学者ドナルド・クヌースによって40年以上前に作られた組版処理ソフトウェア(数学用ワープロ)。
クヌースが数学の本を出す際に、当時のタイプライターで打たれた数式が非常に見づらかったため、出版社とケンカ、もういいオレが作る!と開発された。
のちにプログラマーのレスリー・ランポートがこれを改良し(LaTeX)、さらに使いやすくなった。
数学者が作っただけあって、普通の文章を書くならワードに負ける気がするが、複雑な数式を手っ取り早く作るなら、こちらはかなり使いやすい。ただし、あになんぞ、我が人生で複雑な数式を書かんや(いやない)。
特徴としては、原稿(ソース)はテキストファイルなので汎用性が高い。
また、ワードと違いソースコードを打つので、それがどのように製版されるかはプログラミング中に確認できない(確認にはソースをコンパイルさせる必要がある)。
ちなみに、金儲けのために作ったわけではないというのがクヌースのモットーであるためフリーソフトです。
ソースコードの例
\documentclass[a4j,12pt]{jarticle}
\title{数学}
\author{多分ウィキペディア}
\date{2017年8月3日}
\begin{document}
\maketitle
広義には、超数学(メタ数学)などと呼ばれる枠組みにしたがって公理と推論規則が定められた体系一般を指す。現代的な数学においては、公理に定義される抽象的な構造を、形式論理を共通の枠組みとして用いて研究する。方法論の如何によらず最終的には、数学としての成果というものはほかの自然科学のように実験や観察によるものであってはならない。
\end{document}
※コードを書く際の注意
ソースの行の長さは適度に改行し短めにする。エラーの際には行単位でエラーが報告されるため、行が長いと探すのが面倒。
コメントアウト
%のあとに文章を書くと製版には反映されない、ソースコードの注釈(コメントアウト)となる。
基本設定
文字サイズ
[a4j,15pt]は、A4サイズの紙に12ポイント(ワードと違って12ポイントが最大!)の大きさで文字を表示させろという意味。かっこは[ ]を使う。
文字のサイズをもっと小さく、もしくは大きくする場合は
{\tiny }
{\scriptsize }
{\footnotesize }
{\small }
{\normalsize }
{\large }
{\Large }
{\LARGE }
{\huge }
{\Huge }
の順で大きくなる。
ノーマルサイズはドキュメントクラスの行で設定した文字サイズになり、それがサイズの基準になるので、12ptから10ptに変更するとtiny~Hugeもすべてそれにつられて若干小さくなる。
日付
\date{\today}と打つと自動的に今日の日付にしてくれる。
文体
{jarticle}は、ドキュメントのレイアウトを指定していてジャパンのアーティクルで和文の論文という意味。かっこは{ }を使う。
和文では自動的に段落の最初のマスは空欄にしてくれる。
スペース
LaTeXでは、複数の半角スペースをソースで入力しても、製版ではひとつ分しか空けてくれない。ただし全角スペースでは打った分だけ空白としてくれる。
ドキュメント内のテキストに、空白行を入れると製版では段落を変えてくれる。
\hspece{3cm}のようにスペースの長さを指定することもできる。
縦にスペースを空ける場合は\vspece{3cm}(バーティカルで縦)
強制改行
全角空欄+\\で強制改行(エンターキーの役割)。その場合、自動的に空欄は作られない。
書体変更
書体の変更はたとえば名前の部分だけローマン(rm)にしたいなら
\authior{TASHIRO{\rm TAKAHIRO}}
イタリック体なら
\authior{TASHIRO{\it TAKAHIRO}}
表・グラフ
|で地道に縦線を引く。横線は\hlineでひく。
|と|間にc(センターのc)を入れると線と線の間(セルの中)の文字は中央ぞろえ、l(レフト)だと左揃え、r(ライト)だと右揃えになる。
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\title{表組み}
\author{田代剛大}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
平成21年進路別中学校卒業者数
\begin{tabular}{|c||c|c|c|c|c|c|}\hline
& 高等学校等 & 専修学校 & 専修学校 & 公共職業能力 & & \\
都道府県名 & & (高等課程) & (一般課程)& 開発施設等 & 就職者 & 計\\
& 進学者 & 進学者 & 進学者 & 入学者数 & & \\
\hline \hline
埼玉 & 64,272 & 111 & 24 & 8 & 307 & 64,722\\
\hline
千葉 & 52,439 & 118 & 80 & 30 & 210 & 52,877\\
\hline
東京 & 98,537 & 388 & 242 & 53 & 448 & 99,668\\
\hline
神奈川 & 73,034 & 279 & 103 & 9 & 342 & 73,767 \\
\hline
新潟 & 23,301 & 2 & 4 & 13 & 43 & 23,363\\ \hline
\end{tabular}
\end{document}
数式
数式を書く場合は$と$の間にはさむと、数学の教科書のように表記してくれる。
$$と$$ではさむと、はさまれた数式は中央に並ぶ。
\timesで×のマーク。
\divで÷のマーク(ディヴィジョン)。
\frac{分子}{分母}で分数。
\sqrt2で2の平方根で√2。
^2で2乗
\leqで≦
\geqで≧
数式の通し番号をつけたい場合は\bigin{equation}と\end{equation}で複数の数式を挟むと自動的に式番号をつけてくれる。また、挟まれた部分は自動的に表記が数学になるので$$は不要で、つけるとエラーになる。
コード例:1
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\begin{document}
$$1,4,7,\ldots,22,25,\ldots$$
$$\sum_{k=1}^{n}(k^2+3k)$$
$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin x}{x}=1$$
$$S=\{(x,y)|1\leq x \leq 2,y\in R\}$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
\end{document}
コード例:2
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\begin{document}
\begin{eqnarray*}
\sqrt{15}\times\sqrt{10}
&=&\sqrt{5\times3}\times\sqrt{5\times2}\\
&=&\sqrt{5\times3\times5\times2}\\
&=&\sqrt{5^2\times3\times2}\\
&=&5\sqrt{6} \nonumber\\
\end{eqnarray*}
\begin{eqnarray*}
\frac{3x-y}{2}-\frac{x-4y}{4}&=&\frac{2(3x-y)}{4}-\frac{x-4y}{4}\\
&=&\frac{2(3x-y)-(x-4y)}{4}\\
&=&\frac{6x-2y-x+4y}{4}\\
&=&\frac{5x+2y}{4}
\end{eqnarray*}
%2ページ目
\newpage
\begin{flushleft}
$n$が奇数ならば、$n^2-1$は$8$で割り切れることを示せ。\\
\\
$n$を奇数とおくと$$n=2m^2+1$$($m$は自然数)となるので\\
\begin{eqnarray*}
(2m^2+1)^2-1
&=&4m^2+4m+1-1\\
&=&4m^2+4m\\
&=&4m(m+1)\\
\end{eqnarray*}
$m$と$m+1$は連続する自然数なので、どちらかは必ず偶数となり、その偶数に$4$がかけられるため、$n$が奇数ならば、$n^2-1$は$8$で割り切れる。\\
\end{flushleft}
%3ページ目
\newpage
\begin{flushleft}
$x=a^2+1$のとき\\
\\
$P=\sqrt{x+2a}+\sqrt{x-6a+8}$\\
\\
をaの多項式を用いて表せ。\\
\\
\\
$P=\sqrt{x+2a}+\sqrt{x-6a+8}$に$x=a^2+1$を代入すると\\
\\
$P=\sqrt{a^2+2a+1}+\sqrt{a^2-6a+9}$\\
\\
$\hspace{8mm}=\sqrt{(a+1)^2}+\sqrt{(a-3)^2}$\\
\\
$\hspace{8mm}=|a+1|+|a-3|$\\
\\
ここで場合分けを行うと\\
\\
$3\leq a$のとき\\
$P=a+1+a-3$\\
$\hspace{4mm}=2a-2$\\
\\
$-1 \leq a <3$のとき\\
$P=a+1-a+3$\\
$\hspace{4mm}=4$\\
\\
$a<-1$のとき\\
$P=-a-1-a+3$\\
$\hspace{4mm}=-2a+2$\\
\end{flushleft}
\end{document}
コード例:3
\documentclass[12pt,a4j]{jarticle}
\title{二次方程式の参考書}
\author{16PH5074 田代剛大}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{二次方程式の概要}
二次方程式は、以下のような最大次数が2である方程式である。\\
$$x^2=9$$ \\
$$4x^2=5$$ \\
$$x^2+8x+15=0$$ \\
特徴として、解が必ずしもひとつではなく、多くの場合二通りあるということや、解法が複数あり、どの解法が最も適しているかを、問題ごとに生徒自身が判断しなければならないこと、などが挙げられる。そのため、中学校の数学では難易度が高く、中学校三年生の一学期前半に因数分解や平方根を学習した上で、後半に取り上げられる。\\
\newpage
\section{二次方程式の解法}
二次方程式の解法を難易度順に紹介する。
\\
1.平方根の考え方を利用して解くタイプ\\
$(1) x^2=9$ \\
求める$x$は二乗して9になる数(9の平方根)と考えるので\\
\begin{eqnarray*}
x^2
&=&9\\
x
&=&\pm 3
\end{eqnarray*}
\\
$(2) x^2-3=0$ \\
このような場合は、移項したあとに根号を使う。\\
\begin{eqnarray*}
x^2-3
&=&0\\
x^2
&=&3\\
x
&=&\pm\sqrt3
\end{eqnarray*}
\\
$(3) (x+5)^2-3=0$ \\
( )の中の多項式をひとつの文字として考える。\\
\begin{eqnarray*}
(x+5)^2-3
&=&0\\
(x+5)^2
&=&3\\
x+5
&=&\pm\sqrt3\\
x
&=&-5\pm\sqrt3\\
\end{eqnarray*}
\newpage
\\
2.因数分解をして解くタイプ\\
$(1) x^2+x=0$ \\
各項の共通因数を見つけて( )でくくる。その後、( )の外側を0にする$x$の値、( )の内側を0にする$x$の値を考える。\\
\begin{eqnarray*}
x^2+x
&=&0\\
x(x+1)
&=&0\\
\end{eqnarray*}
$$x=0,x=-1$$\\
\\
$(2) x^2+8x+15=0$ \\
因数分解の公式を使う。足して8になり、かけて15になる、二つの数の組み合わせを考える。その後、左の( )の内側を0にする$x$の値、右の( )の内側を0にする$x$の値を考える。\\
\begin{eqnarray*}
x^2+8x+15
&=&0\\
(x+3)(x+5)
&=&0\\
\end{eqnarray*}
$$x=-3,x=-5$$\\
\\
$(3) x^2-12x+36=0$\\
これも因数分解の公式を使うが、解がひとつに定まるので注意する。\\
\begin{eqnarray*}
x^2-12x+36
&=&0\\
(x-6)(x-6)
&=&0\\
(x-6)^2
&=&0\\
\end{eqnarray*}
$$x=6$$\\
\\
3.完全平方式にして解くタイプ\\
因数分解ができない問題の場合、無理やり平方根の考え方で解けるように$( )^2$の形に表し直す方法。
まず、定数項を右辺に移項し、左辺を$( )^2$の形にするために必要な定数を両辺に加えて解く。
\begin{eqnarray*}
x^2-4x+2
&=&0\\
x^2-4x
&=&-2\\
x^2-4x+4
&=&-2+4\\
(x-2)^2
&=&2\\
x-2
&=&\pm\sqrt2\\
x
&=&2\pm\sqrt2\\
\end{eqnarray*}
\\
4.解の公式を用いて解くタイプ\\
完全平方をする解法を一般化したもの。
二次方程式$ax^2+bx+c=0$($a,b,c$は係数)を完全平方式にして解くと\\
\begin{eqnarray*}
ax^2+bx+c
&=&0\\
ax^2+bx
&=&-c\\
x^2+\frac{bx}{a}
&=&\frac{-c}{a}\\
(x+\frac{b}{2a})^2
&=&\frac{-c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}\\
(x+\frac{b}{2a})^2
&=&\frac{b^2-4ac}{4a^2}\\
x+\frac{b}{2a}
&=&\frac{\pm\sqrt{b^2 -4ac}}{2a}\\
x
&=&\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\\
\end{eqnarray*}
と、二次方程式の解の公式が得られる。この公式にそれぞれの係数$a,b,c$を代入すれば、混合が残る複雑な問題も短い時間で解くことができる。\\
完全平方式で解いたほうが早い問題もあるが、ひとつの判断基準として、$x$の係数が奇数で完全平方の際に分数になってしまう問題、$x^2$に係数がついていて全ての項を$x^2$の係数で等しく割る必要がある問題は、解の公式を使ったほうが早く解ける場合が多い。
\end{document}
・・・てな感じのことをやりました。これは地獄のほんの一部であることをお伝えしたい。

あと、今回は講義を受ける棟がいつもの理科の棟じゃなくて情報処理のエリアだったから、こんなところに海浜幕張的な空中庭園があるんだとか、けっこう前人未踏で

うお、こんなところには第二の学食が!
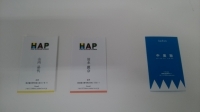
こっちではデザイン科の作品展がやってるぞ気をつけろ!
・・・みたいにひとりデザーテッドアイランドやってて楽しかった。でもプログラムは辛かった。数学は一種免許あきらめる。これを4回もやる根性が私にはない。プログラマーってそう考えると忍耐強いよな。確かに短気ですぐキレるイメージないもんな。
漢文学覚え書き②
2017-08-02 16:46:09 (8 years ago)
参考文献:小川環樹、西田太一郎著『漢文入門』
契舟求剣
「契舟求剣(舟に刻みて剣を求む)」は『呂氏春秋』(『呂覧』)に収録された寓話である。
『呂氏春秋』は、秦の始皇帝の治世に総理大臣だった呂不韋によって編集された、古今の学説や思想を集めた書物で、チャプターが12ヶ月の季節によって分けられていたので、こう呼ばれる。日本では荻生徂徠が翻訳を行っている。
現代語訳
楚の国の人で、揚子江を渡る者がいた。
その剣を舟から水中に落としてしまった。
すると、にわかに舟に目印を刻んで
「我が剣が落ちたのはこの場所である。」と言った。
その後、舟が止まると、
舟に刻んだ目印のところから、水に入って剣を探した。
舟はすでに移動しており、剣は移動していない。
このように剣を探すとは、まあほんとうに見当違いではないか。
古くさい制度でその国を治めるのは、これと同じである。
時勢はすでに変化しているというのに、法は変化していない。
この法をもって国を治めようとするのは、どうして難しくないといえるだろうか?(いや難しい)
揚子江のほとりを過ぎる者がいた。
すると、(ある人が)小さい子を引いて川の中に投げ込もうとし、
子が声を出して泣いているのを見た。
そのわけを問うた。
その人は答えた。「この子の父は上手に泳げた。」
その父親が上手に泳げても、
その子どもがどうして急に上手に泳げるものだろうか(いやムリ)。
原文
楚人有渉江者、・・・①
其剣自舟中墜於水、
遽刻其舟曰、・・・②
是吾剣之所従墜、
舟止、
従其所契者、入水求之、・・・③
舟已行矣、而剣不行、・・・④
求剣若此、不亦惑乎、・・・⑤
以此故法為其國、
與此同、
時已徙矣、
而法不徙、
以此為治、
豈不難哉、・・・⑥
有過於江上者、・・・①
見人方引嬰児而欲投之江中、
嬰児啼、
人問其故、
曰、此其父善游、
其父雖善游、
其子豈遽善游哉、・・・⑥
留意すべき文法事項
①「楚人有二渉レ江者一。」(そひとにこうをわたるものあり)
「有下過二於江上一者上、」(こうじょうをすぐるものあり)
返り点も少なく、書き下し文にしやすいので、授業最初の肩慣らしとしてうってつけである。
ちなみに、テキストによれば「江」と書くと基本的には「長江」すなわち「揚子江」を指し、同様に「河」と書くと「黄河」を指すという。
②「遽刻二其舟一曰」(にわかにそのふねにきざみていわく)
「遽」は、「にはかに」と読み、「突然に」という意味の形容動詞である。
③「従二其所レ刻者一、入レ水求レ之」(そのきざみしところのものより、みずにいりてこれを もとむ)
「従」は「より」と読む。
④「舟已行矣、而剣不レ行、」(ふねはすでにゆけり、しかもけんはゆかず)
「已」は「すでに」と読む。
置き字の「矣」に注意させる。
「而剣不行」の「而」は、置き字ではなく「しかも」と読む。
文中の「而」は読まないが、このように文頭にあると「しかも」「しかるに」など読む。
⑤「求レ剣若レ此、不二亦惑一乎、」(けんをもとむることかくのごときは、またまどいならずや)
「若」は、「ごときは」と読む。
「亦」は「また」と読む。
「惑」は、「まどいなら」となる。
この文章は詠嘆で、意味は「まあほんとうに~ではないか」となる。
⑥「豈不レ難哉、」(あにかたからずや)
「豈遽善游哉、」(あになんぞよくおよがんや)
どちらも反語的な詠嘆で「どうして~だろうか、いや~でない。」と訳する。
指導上のポイント
この文章は二部構成になっていて、まるで歌の歌詞の一番と二番のように出だしと末尾の文章が対応している。
内容もリンクしていて、一番では、時勢は移り変わってゆくこと、二番では、世代も交代していくことを説いている。
このように、漢文は教訓を十中八九、例え話(寓話)にする。
つまり、時代の流れを揚子江の流れに見立て、動いている船に乗っていながら、動かない剣(古い制度)に固執することを戒めているのである。
まずは、こういったメタファーに気づき、そこから情景をイメージしていった方が学生は内容を理解しやすい。
そこで、むしろ中盤の「時已徙矣、而法不徙、以此為治、豈不難哉、」から訓読させ、作者が伝えたい教訓を理解してから、では今回はどういった例え話をやっているのだろう?と投げかける授業展開も効果的だと考えられる。
いずれにせよ、漢文は寓話であるという点と、注意すべき助辞を押さえさせれば、漢文の内容理解がパターン化し、効率よく訓読できるようになるはずである。
契舟求剣
「契舟求剣(舟に刻みて剣を求む)」は『呂氏春秋』(『呂覧』)に収録された寓話である。
『呂氏春秋』は、秦の始皇帝の治世に総理大臣だった呂不韋によって編集された、古今の学説や思想を集めた書物で、チャプターが12ヶ月の季節によって分けられていたので、こう呼ばれる。日本では荻生徂徠が翻訳を行っている。
現代語訳
楚の国の人で、揚子江を渡る者がいた。
その剣を舟から水中に落としてしまった。
すると、にわかに舟に目印を刻んで
「我が剣が落ちたのはこの場所である。」と言った。
その後、舟が止まると、
舟に刻んだ目印のところから、水に入って剣を探した。
舟はすでに移動しており、剣は移動していない。
このように剣を探すとは、まあほんとうに見当違いではないか。
古くさい制度でその国を治めるのは、これと同じである。
時勢はすでに変化しているというのに、法は変化していない。
この法をもって国を治めようとするのは、どうして難しくないといえるだろうか?(いや難しい)
揚子江のほとりを過ぎる者がいた。
すると、(ある人が)小さい子を引いて川の中に投げ込もうとし、
子が声を出して泣いているのを見た。
そのわけを問うた。
その人は答えた。「この子の父は上手に泳げた。」
その父親が上手に泳げても、
その子どもがどうして急に上手に泳げるものだろうか(いやムリ)。
原文
楚人有渉江者、・・・①
其剣自舟中墜於水、
遽刻其舟曰、・・・②
是吾剣之所従墜、
舟止、
従其所契者、入水求之、・・・③
舟已行矣、而剣不行、・・・④
求剣若此、不亦惑乎、・・・⑤
以此故法為其國、
與此同、
時已徙矣、
而法不徙、
以此為治、
豈不難哉、・・・⑥
有過於江上者、・・・①
見人方引嬰児而欲投之江中、
嬰児啼、
人問其故、
曰、此其父善游、
其父雖善游、
其子豈遽善游哉、・・・⑥
留意すべき文法事項
①「楚人有二渉レ江者一。」(そひとにこうをわたるものあり)
「有下過二於江上一者上、」(こうじょうをすぐるものあり)
返り点も少なく、書き下し文にしやすいので、授業最初の肩慣らしとしてうってつけである。
ちなみに、テキストによれば「江」と書くと基本的には「長江」すなわち「揚子江」を指し、同様に「河」と書くと「黄河」を指すという。
②「遽刻二其舟一曰」(にわかにそのふねにきざみていわく)
「遽」は、「にはかに」と読み、「突然に」という意味の形容動詞である。
③「従二其所レ刻者一、入レ水求レ之」(そのきざみしところのものより、みずにいりてこれを もとむ)
「従」は「より」と読む。
④「舟已行矣、而剣不レ行、」(ふねはすでにゆけり、しかもけんはゆかず)
「已」は「すでに」と読む。
置き字の「矣」に注意させる。
「而剣不行」の「而」は、置き字ではなく「しかも」と読む。
文中の「而」は読まないが、このように文頭にあると「しかも」「しかるに」など読む。
⑤「求レ剣若レ此、不二亦惑一乎、」(けんをもとむることかくのごときは、またまどいならずや)
「若」は、「ごときは」と読む。
「亦」は「また」と読む。
「惑」は、「まどいなら」となる。
この文章は詠嘆で、意味は「まあほんとうに~ではないか」となる。
⑥「豈不レ難哉、」(あにかたからずや)
「豈遽善游哉、」(あになんぞよくおよがんや)
どちらも反語的な詠嘆で「どうして~だろうか、いや~でない。」と訳する。
指導上のポイント
この文章は二部構成になっていて、まるで歌の歌詞の一番と二番のように出だしと末尾の文章が対応している。
内容もリンクしていて、一番では、時勢は移り変わってゆくこと、二番では、世代も交代していくことを説いている。
このように、漢文は教訓を十中八九、例え話(寓話)にする。
つまり、時代の流れを揚子江の流れに見立て、動いている船に乗っていながら、動かない剣(古い制度)に固執することを戒めているのである。
まずは、こういったメタファーに気づき、そこから情景をイメージしていった方が学生は内容を理解しやすい。
そこで、むしろ中盤の「時已徙矣、而法不徙、以此為治、豈不難哉、」から訓読させ、作者が伝えたい教訓を理解してから、では今回はどういった例え話をやっているのだろう?と投げかける授業展開も効果的だと考えられる。
いずれにせよ、漢文は寓話であるという点と、注意すべき助辞を押さえさせれば、漢文の内容理解がパターン化し、効率よく訓読できるようになるはずである。
- Calendar
<< January 2026 >> Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- search this site.
- tags
-
- 漫画 (387)
- 脚本 (243)
- 映画 (235)
- 雑記 (163)
- ゲーム (156)
- 本 (116)
- 教育 (107)
- 生物学 (105)
- 科学 (93)
- 社会学 (81)
- 歴史 (72)
- テレビ (71)
- 芸術 (61)
- 政治 (50)
- 数学 (40)
- 進化論 (40)
- 資格試験 (38)
- 情報 (38)
- サイト・ブログ (37)
- 語学 (37)
- 映画論 (36)
- 物理学 (33)
- 哲学 (32)
- 恐竜 (29)
- 育児 (28)
- 文学 (26)
- 化学 (25)
- 論文 (22)
- PIXAR (22)
- 心理学 (18)
- 地学 (16)
- 気象学 (15)
- 地理学 (15)
- 技術 (13)
- 経済学 (12)
- 医学 (11)
- 玩具 (9)
- 司書 (8)
- 法律学 (7)
- 対談 (5)
- スポーツ (4)
- 映画の評価について (1)
- プロフィール (1)
- archives
-
- 202601 (2)
- 202512 (4)
- 202511 (15)
- 202510 (8)
- 202509 (5)
- 202508 (3)
- 202507 (3)
- 202506 (3)
- 202505 (1)
- 202504 (2)
- 202503 (2)
- 202502 (2)
- 202501 (1)
- 202412 (2)
- 202411 (6)
- 202410 (2)
- 202409 (4)
- 202408 (4)
- 202407 (7)
- 202406 (27)
- 202405 (11)
- 202404 (4)
- 202403 (23)
- 202402 (22)
- 202401 (15)
- 202312 (4)
- 202311 (7)
- 202310 (2)
- 202309 (8)
- 202308 (9)
- 202307 (8)
- 202306 (5)
- 202305 (15)
- 202304 (4)
- 202303 (4)
- 202302 (2)
- 202301 (4)
- 202212 (15)
- 202211 (7)
- 202210 (5)
- 202209 (4)
- 202208 (4)
- 202207 (7)
- 202206 (2)
- 202205 (5)
- 202204 (3)
- 202203 (2)
- 202202 (5)
- 202201 (6)
- 202112 (6)
- 202111 (4)
- 202110 (6)
- 202109 (7)
- 202108 (5)
- 202107 (8)
- 202106 (4)
- 202105 (8)
- 202104 (4)
- 202103 (6)
- 202102 (10)
- 202101 (3)
- 202012 (12)
- 202011 (3)
- 202010 (4)
- 202009 (5)
- 202008 (6)
- 202007 (4)
- 202006 (4)
- 202005 (4)
- 202004 (7)
- 202003 (5)
- 202002 (6)
- 202001 (8)
- 201912 (6)
- 201911 (5)
- 201910 (3)
- 201909 (4)
- 201908 (10)
- 201907 (3)
- 201906 (6)
- 201905 (10)
- 201904 (3)
- 201903 (7)
- 201902 (8)
- 201901 (5)
- 201812 (7)
- 201811 (12)
- 201810 (7)
- 201809 (5)
- 201808 (10)
- 201807 (5)
- 201806 (19)
- 201805 (14)
- 201804 (11)
- 201803 (15)
- 201802 (4)
- 201801 (6)
- 201712 (4)
- 201711 (3)
- 201710 (11)
- 201709 (9)
- 201708 (15)
- 201707 (7)
- 201706 (4)
- 201705 (5)
- 201704 (6)
- 201703 (7)
- 201702 (6)
- 201701 (3)
- 201612 (3)
- 201611 (7)
- 201610 (7)
- 201609 (2)
- 201608 (8)
- 201607 (8)
- 201606 (7)
- 201605 (3)
- 201604 (4)
- 201603 (8)
- 201602 (3)
- 201601 (2)
- 201512 (3)
- 201511 (3)
- 201510 (4)
- 201509 (4)
- 201508 (8)
- 201507 (17)
- 201506 (2)
- 201505 (5)
- 201504 (9)
- 201503 (20)
- 201502 (7)
- 201501 (4)
- 201412 (5)
- 201411 (3)
- 201410 (2)
- 201409 (3)
- 201408 (3)
- 201407 (3)
- 201406 (12)
- 201405 (6)
- 201404 (7)
- 201403 (5)
- 201402 (12)
- 201401 (9)
- 201312 (6)
- 201311 (9)
- 201310 (8)
- 201309 (6)
- 201308 (6)
- 201307 (6)
- 201306 (10)
- 201305 (10)
- 201304 (23)
- 201303 (17)
- 201302 (16)
- 201301 (5)
- 201212 (10)
- 201211 (4)
- 201210 (18)
- 201209 (4)
- 201208 (30)
- 201207 (7)
- 201206 (4)
- 201205 (6)
- 201204 (4)
- 201203 (4)
- 201202 (3)
- 201201 (3)
- 201112 (4)
- 201111 (7)
- 201110 (3)
- 201109 (9)
- 201108 (3)
- 201107 (7)
- 201106 (2)
- 201105 (11)
- 201104 (7)
- 201103 (14)
- 201102 (19)
- 201101 (27)
- 201012 (25)
- 201011 (70)
- 201010 (34)
- 201009 (30)
- 201008 (42)
- 201007 (44)
- 201006 (29)
- 201005 (37)
- 201004 (50)
- 201003 (44)
- 201002 (48)
- 201001 (38)
- 200912 (20)
- recent trackback
- others
-
- RSS2.0
- hosted by チカッパ!
- HEAVEN INSITE(本サイト)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356