バス停――
金吾「本当に伊賀の国に行くのか?」
カイト「翼さんを助け出さないと・・・」
金吾「そうか・・・道中気をつけるんじゃぞ。」
「え?じいさんは助けに行かないの?」
「わしはここに留まりこの村を守る義務がある・・・」
千代女「なんの役にもたってないじゃない。はは~ん怖いんでしょ」
「わしがじきじきに出陣する相手でもないと言っとるんじゃ」
ため息をつく千代女「いいわ、私がついてってあげる。」
「千代女さんが?」
「あのおじいちゃんよりは役に立つから」
「ふん、勝手にしろ」
携帯電話を取り出す千代女。
「伊賀の国へはコミュニティバスが出てないからタクシー呼ぶね」
「いいんですか?」
「これでもヘッジファンドで稼いでるから。」
「西洋かぶれが・・・」
村の喫茶店からその様子を見るサラリーマン風の男。
「金吾は村を出ませんでした、どうします??」
電話の相手「前回の失敗は彼らを見くびったことによるものだよ。」
「了解しました。待機します。」
「いや~しかしご主人、このご飯おいしいですね~」
「日本一美味しいでしょ。甲賀米コシヒカリだよ」
「実はワタクシ商社をやってまして・・・ここのお米を買い付けてもいいですか?」
「本当かい」
「ええ、とりあえず500トンほどJAの二倍の金額で買取りましょう」
「ちょ、ちょっと待ってくれ!!名刺もらっていい??」
「丹羽と申します――」
タクシーの車中――
千代女「いや~青春って感じだよね」
カイト「え?」
「好きな女の子のために一途に行動できるって」
「そ、そういうわけじゃ・・・」
「私にもそういう時代あったな・・・その翼ちゃんていうのはどんな子なの?」
「・・・。自分のことを自分以上に買ってくれている、そんな子です」
「あら、そんな子は大切にしなきゃダメよ・・・
大人になってからの恋は損得勘定になっていけないわ・・・
まるでナスダックの先物取引のようにね」
「あの・・・ありがとうございます。」
「ん?」
「ついて来てくれて・・・
伊賀の忍者には殺されかけたことがあって、正直怖かったんです・・・」
「ごめんね、うちのお父さんのせいで・・・
今回はだいじょうぶ、私もこれでも忍者の末裔だから・・・」
財布から御札のようなものを取り出す千代女。
タクシーが止まる
「さて・・・ついたわ」
伊賀エージェンシー本部基地――
軍事境界線のような防壁と監視カメラ、見張り台がある。
カイト「ここって本当に日本・・・」
「治外法権ってところかな・・・闇に葬りたい機密情報が日本中から集まっているから。
あの看板は殺傷武器の使用が認められているって意味ね」
USE OF DEADLY FORCE AUTHORIZED
「ど、どうすれば・・・」
?「は~はは!ようこそ我が砦へ!」
警報が鳴ってゲートが開く。
カイト「!!」
千代女「知り合い?」
長門に指を指すカイト「あ、あいつに殺されかけたんですよ!!」
長門「前回の戦いは引き分けたが・・・今度は私が勝つ・・・!」
カイト「嘘つけ、明らかに負けてただろ!」
「卑怯にも3対1で一度に襲いかかってきてな・・・
なので、今度は集団でやってきました」
武装した伊賀忍者が集まってくる。
「相変わらず最低だコイツ!」
「私の獲物は、その小僧だけだ・・・ご婦人は下がっててもらおう」
「下がってください、千代女さん・・・!」
「減俸、停職処分の借りは返させてもらうぞ小僧!」
「俺に言われても・・・」
「一斉射撃用意~!」
「え・・・マジで!?高校生相手にそこまでやる?」
「撃て~~!」
機関銃を乱射する忍者部隊
「式神結界!!」
千代女がその刹那バリアを張る。
銃弾が跳ね返って機関銃を破壊していく。
長門「なんだと!?」
千代女「今よカイト君!」
カイト「野球をなめんな~~!!」
石のつぶてをバットでノックするカイト。
長門の顔面を直撃する。「ぎゃっ!」
忍者たち「隊長!!」
「そこまで!」
その声で忍者たちが攻撃態勢を解く。
「なるほど・・・わが娘が一目置いただけある・・・」
カイト「え?」
百地「風間カイトくんだね?私は伊賀エージェンシー社主、百地丹波」
「もしかして・・・」
「翼の父だ」
長門「おのれ、勝負は終わってないぞ、貴様ら・・・!」
「もういい、長門くん。」
「しかし社長・・・!」
「キミはクビだ。そこのモブのキミ。」
モブ「わたくしですか?」
「明日から隊長をやりなさい。」
モブ「よっしゃ~!」
カイト「・・・・・・。」
カイト「そ、そういえば翼さんは・・・!!!?」
百地「ああ・・・」
カイト「無事なんですか!?」
フランス人形のようなフリフリの服を着た翼が駆け寄ってくる。
「カイトさん!」
「翼さん!!」
カイトに抱きつく翼
「なんでここに・・・!?」
「いきなりいなくなっちゃったから・・・心配でさ・・・
それに手紙に助けてって・・・」
「え?助けて・・・?」
咳払いをする百地。
離れる二人。
「それで私のために、たった一人でこんな危険なところに・・・」
「いや・・・望月のじいさんの娘さんが連れてってくれて・・・
すごかったんだよ・・・まるで魔法使いで・・・!」
「どこですか?」
「あれ??いない・・・」
百地「まあ、こんなところで立ち話もなんだ。ようこそ伊賀の国へ」
『風と翼:REVIVE』脚本②
2018-06-25 21:05:31 (7 years ago)
滋賀県近江――
木炭バスに乗るカイト。
回想シーン
「近江の国に行くなんてお母さんは許しません!
だいたい学校はどうするの!あんた野球だけじゃなくて高校も辞めるつもりなの!?」
「鳥インフルエンザにかかったとか適当に嘘ついておいてよ」
「コラカイト!おかあさんに嘘を付かせるのか!そんな子に育てた覚えはないぞ!
お前はハマの大魔神を目指して毎日黙って素振りをやっていればいいんだ!」
「もういいよ!無断欠席するから!」
「・・・・・・・・。」
向かいのシートに目をやるカイト。
翼の影が映る。
「思えば野球を辞めた自分を慕ってくれたのはあの子だけだったな・・・」
望月村忍者屋敷――
カイト「お~い、じいさ~ん・・・老人会かな・・・?」
(くくく・・・この忍者屋敷に迷い込みしものは生きては帰れんぞ・・・!)
「あそうか、一応ここってそういうところか・・・」
回転扉が回る。
金吾「咽び泣くがいい!わしの催涙ガスで!」
屁をこく。
「ぎゃああ会って早々なにすん・・・!!」
すかしっぺが出る。
「あ、あれ・・・?臭くない・・・」
金吾「!!」
崩れ落ちる金吾
「わ・・・わしはもうダメじゃ~」
「へ・・・?」
「最近勢いのあるくさい屁が出んのじゃ・・・」
(よかったじゃん・・・)
「とうとうわしもお迎えが来たようじゃ・・・死ぬ前に孫の顔が見たかったのう・・・」
「いやいや・・・またイモでも食えば昔みたいな激臭が出せるって・・・出して欲しくないけど・・・」
「若かりし頃はこの屁に着火してオゾン層あたりまで飛べたんじゃ・・・」
「はいはい・・・すごいすごい・・・ってそれほんとにすごいね。」
「で、なんじゃ!相模のリア充!衰えたわしを見て嘲笑いに来たのか!!」
(いきなり怒り出した・・・!)
「いや、違うんだよ、翼さんが突然いなくなっちゃったんだ」
「ま、あやつも忍びだからの」
「この手紙があって・・・心配でさ」
「ほう、わしに読めってか。」
「うん」
「つまり、自分ひとりでは何もできないから、この甲賀忍者総大将望月金吾を頼って、わざわざ相模から近江へ・・・!」
「そうですよ!」
「よっしゃ、そこの葉月ルーペとって」
老眼鏡を渡すカイト。
「・・・・・・。」
「え~なになに、草書体で読みづれえな・・・
カイトさんへ、突然姿を消すことをお許し下さい。
実は家族に不幸があり私は故郷の伊賀の国へ帰ることになりました。
相模高校での日々は短かったですが、カイトさんには本当にお世話になりました。
いつも私のことを気にかけてくれてありがとう、野球頑張ってね。 翼
だって。実家に帰ったんじゃな。」
「実家って・・・
伊賀の忍者ってこの前襲ってきた、あいつみたいな連中でしょ」
「クソ野郎どもじゃな」
「そんな集団のところへ戻って大丈夫なんですか?」
「家族に不幸って書いてあるからな・・・のっぴきならないことがあったんじゃろうて」
「でも・・・」
「お前も家に帰ってその野球とやらに興じればいいじゃろ。
わしは残り少ない余生を静かにおくるんじゃ!・・・ん?」
「ん?」
「まあいいか・・・」
「え?なになに!!」
「この手紙、最後だけ神代文字で書かれておる」
「なにそれ?」
「忍者が使う暗号のようなもんじゃ」
「読めますか?」
「ええと・・・テケスタだって。そんなスタジアムあったか?」
「ん~と、ない。」
「じゃあ、意味はないじゃろ」
千代女「それって“助けて”じゃないの?」
カイト「誰ですか?」
金吾「あ、ああ。わしの娘の千代女じゃ・・・帰省しておってな」
「いつもウチのハゲおやじがお世話になってます。お茶でも入れますね」
「いえ、お構いなく・・・
・・・あんな美人な娘さんいたの!?」
「わしに似ていい女じゃろ」
「いや、まったく似てないと思いますけど・・・」
「はい、粗茶ですが・・・
しかし、こんな村に都会派な若い男の子が来てくれるなんて。歴史ファンとか?
私も丸の内でOLやってるんですよ。」
「ふん、この娘、田舎が嫌いとか抜かしおって、どこぞの男と駆け落ちしおって・・・
その挙句に即行で離婚、愚かなもんじゃ・・・」
「そういうこと言うと、一生孫の顔は見せないからね」
「なにを偉そうに、親権は旦那のほうじゃろうが」
「まったく、体調が悪いって言うからわざわざ駆けつけてあげたのに・・・こんなトラップってあると思います?カイト君・・・」
「トラップ・・・」
「そうだった!翼さんが危ない!!」
木炭バスに乗るカイト。
回想シーン
「近江の国に行くなんてお母さんは許しません!
だいたい学校はどうするの!あんた野球だけじゃなくて高校も辞めるつもりなの!?」
「鳥インフルエンザにかかったとか適当に嘘ついておいてよ」
「コラカイト!おかあさんに嘘を付かせるのか!そんな子に育てた覚えはないぞ!
お前はハマの大魔神を目指して毎日黙って素振りをやっていればいいんだ!」
「もういいよ!無断欠席するから!」
「・・・・・・・・。」
向かいのシートに目をやるカイト。
翼の影が映る。
「思えば野球を辞めた自分を慕ってくれたのはあの子だけだったな・・・」
望月村忍者屋敷――
カイト「お~い、じいさ~ん・・・老人会かな・・・?」
(くくく・・・この忍者屋敷に迷い込みしものは生きては帰れんぞ・・・!)
「あそうか、一応ここってそういうところか・・・」
回転扉が回る。
金吾「咽び泣くがいい!わしの催涙ガスで!」
屁をこく。
「ぎゃああ会って早々なにすん・・・!!」
すかしっぺが出る。
「あ、あれ・・・?臭くない・・・」
金吾「!!」
崩れ落ちる金吾
「わ・・・わしはもうダメじゃ~」
「へ・・・?」
「最近勢いのあるくさい屁が出んのじゃ・・・」
(よかったじゃん・・・)
「とうとうわしもお迎えが来たようじゃ・・・死ぬ前に孫の顔が見たかったのう・・・」
「いやいや・・・またイモでも食えば昔みたいな激臭が出せるって・・・出して欲しくないけど・・・」
「若かりし頃はこの屁に着火してオゾン層あたりまで飛べたんじゃ・・・」
「はいはい・・・すごいすごい・・・ってそれほんとにすごいね。」
「で、なんじゃ!相模のリア充!衰えたわしを見て嘲笑いに来たのか!!」
(いきなり怒り出した・・・!)
「いや、違うんだよ、翼さんが突然いなくなっちゃったんだ」
「ま、あやつも忍びだからの」
「この手紙があって・・・心配でさ」
「ほう、わしに読めってか。」
「うん」
「つまり、自分ひとりでは何もできないから、この甲賀忍者総大将望月金吾を頼って、わざわざ相模から近江へ・・・!」
「そうですよ!」
「よっしゃ、そこの葉月ルーペとって」
老眼鏡を渡すカイト。
「・・・・・・。」
「え~なになに、草書体で読みづれえな・・・
カイトさんへ、突然姿を消すことをお許し下さい。
実は家族に不幸があり私は故郷の伊賀の国へ帰ることになりました。
相模高校での日々は短かったですが、カイトさんには本当にお世話になりました。
いつも私のことを気にかけてくれてありがとう、野球頑張ってね。 翼
だって。実家に帰ったんじゃな。」
「実家って・・・
伊賀の忍者ってこの前襲ってきた、あいつみたいな連中でしょ」
「クソ野郎どもじゃな」
「そんな集団のところへ戻って大丈夫なんですか?」
「家族に不幸って書いてあるからな・・・のっぴきならないことがあったんじゃろうて」
「でも・・・」
「お前も家に帰ってその野球とやらに興じればいいじゃろ。
わしは残り少ない余生を静かにおくるんじゃ!・・・ん?」
「ん?」
「まあいいか・・・」
「え?なになに!!」
「この手紙、最後だけ神代文字で書かれておる」
「なにそれ?」
「忍者が使う暗号のようなもんじゃ」
「読めますか?」
「ええと・・・テケスタだって。そんなスタジアムあったか?」
「ん~と、ない。」
「じゃあ、意味はないじゃろ」
千代女「それって“助けて”じゃないの?」
カイト「誰ですか?」
金吾「あ、ああ。わしの娘の千代女じゃ・・・帰省しておってな」
「いつもウチのハゲおやじがお世話になってます。お茶でも入れますね」
「いえ、お構いなく・・・
・・・あんな美人な娘さんいたの!?」
「わしに似ていい女じゃろ」
「いや、まったく似てないと思いますけど・・・」
「はい、粗茶ですが・・・
しかし、こんな村に都会派な若い男の子が来てくれるなんて。歴史ファンとか?
私も丸の内でOLやってるんですよ。」
「ふん、この娘、田舎が嫌いとか抜かしおって、どこぞの男と駆け落ちしおって・・・
その挙句に即行で離婚、愚かなもんじゃ・・・」
「そういうこと言うと、一生孫の顔は見せないからね」
「なにを偉そうに、親権は旦那のほうじゃろうが」
「まったく、体調が悪いって言うからわざわざ駆けつけてあげたのに・・・こんなトラップってあると思います?カイト君・・・」
「トラップ・・・」
「そうだった!翼さんが危ない!!」
『風と翼:REVIVE』脚本①
2018-06-25 21:00:10 (7 years ago)
ワンスアポンタイム――
今川重工役員室。
黒服たちが役員室を制圧する。
立ち上がる役員「なんだきみたちは!」
柴田「この会社は我が尾張財団が乗っ取った!」
「バカな・・・!」
会長の椅子に座る信長「今川会長は引退したよ」
テレビ画面を見る今川会長。
会長の家族が忍者に銃を突きつけられている。
アタッシュケースを置く丹羽長秀。
丹羽「ご苦労だったね三太夫。うちのボスは礼は言わないが、報酬はしっかり払う主義でね。」
百地「どんな人間も家族に危害を加えればたいてい操れる・・・」
名古屋の弱小ベンチャー企業が、創業200年の大企業を敵対的に買収した・・・
これにより日本経済の主導権は東海工業地域から中京工業地帯に移った。
これが世に言う桶狭間のTOBである・・・!
風と翼:REVIVE
現在――
相模高校校門。
翼「はわわ・・・私みたいな田舎者がこんな中核都市のハイスクールに受け入れてもらえるのでしょうか・・・」
カイト「緊張することないよ、徐々に慣れていけばいいから。
まあ、母校を甲子園に連れて行きかけたオレレベルになると学校のスターと呼ばれるのは不可避だけどね」
生徒たちが駆け寄ってくる「あ!いたいた!!」きゃ~!
「さすがカイトさん、すごい人気ですね・・・!」
「ファンレターをクラス別に仕分けるのが大変なんだよ・・・」
カイトを素通りして翼に群がる生徒たち
「ねえねえ!百地さんって忍者なんでしょ!?」
「すご~い!今度忍法とか見せて!!」
「ニンニンとかゴザルとかって言うの?」
翼「あ、あれはテレビの話じゃないでしょうか・・・」
「かわい~」
カイト「・・・・・・。」
教室に向かう二人。
翼「はわわ・・・私高校の勉強についていけるか心配です・・・」
カイト「だいじょうぶ、オレが教えてやるから」
翼「ありがとうございます・・・!」
「いいかい、1/2と1/3を足すと2/5になるんだ」
「勉強になります・・・!」
「なあに簡単なことさ」
先生「テスト返却しま~す」
翼63点
カイト8点「・・・・・・。」
体育の走り高跳び。
カイト「おりゃああああ!」
記録2m11センチ!
「すげえ!やはり過去の人でも元スポーツ選手だな!」
「ホントホント!昔あたしがファンだったくらいのことはある!」
「てるちゃん、また好きになったんじゃないの?」
「ちょ・・・バカ言わないでよ、あんなオワコン」
(聞こえるんだけど・・・)
翼ちゃん記録2m15センチ!高校女子の記録更新!
「えええええええええええええ」
「すごすぎる!!さすが忍者!!!」
「あの野球バカよりも飛んでるじゃねーか!」
カイト「・・・・・・!!」
体育館の裏で落ち込むカイト。
翼「あ、こんなところに・・・
これカイトさんが好きな焼きそばパン・・・購買で買ってきました」
「ありがとう・・・」
「となりいいですか?」
「どうぞ」
「・・・・・・」
翼「あ・・・あの・・・」
カイト「・・・君はなんでもできるんだね・・・」
「そ、そんなことないですよ・・・
「ぼくには野球しかなかった・・・
両親がベイスターズの熱狂的ファンでね・・・
小さい頃から将来の夢はプロ野球選手と決まっていた・・・
親の期待に応えてこれでも頑張ったつもりさ・・・
それがこのざまだよ・・・
唯一の取り柄を自ら台無しにしてしまったのさ」
「カイトさん・・・」
「野球を辞めて以来、親とは口も聞いてない・・・なんか気まずくてね」
翼「・・・・・・」
相模高校野球部監督室。
北条監督「え?風間くんを部に戻せ?」
「お願いいたします監督殿・・・!」
「で、でもあの処分は、私だけじゃなくて学校理事会が決めたもので・・・その・・・」
「ではその理事会にかけあっていただけませんか??」
「い、いや~・・・しかしカイト君も余計なことするよ・・・
部内の揉め事に首を突っ込まなければ、うちの部も新聞沙汰にならずに甲子園に行けたのに・・・」
「部のいじめを見て見ぬ振りをすればよかったとおっしゃるのですか??」
「そういうわけじゃないけど・・・」
「ではカイトさんを部に戻していただけるんですね?」
「そういうわけでもないけど~・・・」
「・・・・指揮官としてあるまじき煮え切らない態度・・・!
かくなる上は・・・!」
刀を取り出す。
切腹しようとする翼「この翼の命と引き換えに~~!!」
悲鳴を上げる北条監督「ひ~!!」
マスコミの追求。
日本刀の所持はいつからなんですか!!
自殺の動機はなんだったんですか!!??
クラスでいじめがあったんですか!?
モンゴルへ行っちゃったりするんですか!!?
私の高校生活は終わった・・・
そしたら変な人が来た・・・
長門「は~はは・・・!切腹で新聞一面とは、かつて惚れた女として恥ずかしいぞソードダンサー!」
翼「な、なにしに現れたんですか!
この前カイトさんに退治されたのに、再び甲賀の里を・・・!?」
長門「何も言わずに我々についてきてもらおう」
翼「絶対嫌です」
長門「お前の親の頼みでもか?」
翼「え・・・?」
・
相模高校の廊下。
カイトのもとに集まってくる学生たち
「カイト君野球部復帰おめでとう!!」
「そういや、新聞読んだ?」
「いや~まさか本当に日本刀を所持していたなんて、やっぱり危ないやつだったんだね。退学になってよかった・・・」
「割腹自殺を試みたんだって・・・絶対頭病んでるよ」
「今年最後の夏、甲子園に連れてってね!応援してるから」
「・・・悪いけど自分の力で行ってくれ・・・」
「え?」
「オレは野球部には戻らない」
下駄箱に手紙が入っているのを見つける
「翼さん・・・!?」
手紙を開ける。
「そ・・・草書体で読めねえ!!!
これを読めるのは・・・」
今川重工役員室。
黒服たちが役員室を制圧する。
立ち上がる役員「なんだきみたちは!」
柴田「この会社は我が尾張財団が乗っ取った!」
「バカな・・・!」
会長の椅子に座る信長「今川会長は引退したよ」
テレビ画面を見る今川会長。
会長の家族が忍者に銃を突きつけられている。
アタッシュケースを置く丹羽長秀。
丹羽「ご苦労だったね三太夫。うちのボスは礼は言わないが、報酬はしっかり払う主義でね。」
百地「どんな人間も家族に危害を加えればたいてい操れる・・・」
名古屋の弱小ベンチャー企業が、創業200年の大企業を敵対的に買収した・・・
これにより日本経済の主導権は東海工業地域から中京工業地帯に移った。
これが世に言う桶狭間のTOBである・・・!
風と翼:REVIVE
現在――
相模高校校門。
翼「はわわ・・・私みたいな田舎者がこんな中核都市のハイスクールに受け入れてもらえるのでしょうか・・・」
カイト「緊張することないよ、徐々に慣れていけばいいから。
まあ、母校を甲子園に連れて行きかけたオレレベルになると学校のスターと呼ばれるのは不可避だけどね」
生徒たちが駆け寄ってくる「あ!いたいた!!」きゃ~!
「さすがカイトさん、すごい人気ですね・・・!」
「ファンレターをクラス別に仕分けるのが大変なんだよ・・・」
カイトを素通りして翼に群がる生徒たち
「ねえねえ!百地さんって忍者なんでしょ!?」
「すご~い!今度忍法とか見せて!!」
「ニンニンとかゴザルとかって言うの?」
翼「あ、あれはテレビの話じゃないでしょうか・・・」
「かわい~」
カイト「・・・・・・。」
教室に向かう二人。
翼「はわわ・・・私高校の勉強についていけるか心配です・・・」
カイト「だいじょうぶ、オレが教えてやるから」
翼「ありがとうございます・・・!」
「いいかい、1/2と1/3を足すと2/5になるんだ」
「勉強になります・・・!」
「なあに簡単なことさ」
先生「テスト返却しま~す」
翼63点
カイト8点「・・・・・・。」
体育の走り高跳び。
カイト「おりゃああああ!」
記録2m11センチ!
「すげえ!やはり過去の人でも元スポーツ選手だな!」
「ホントホント!昔あたしがファンだったくらいのことはある!」
「てるちゃん、また好きになったんじゃないの?」
「ちょ・・・バカ言わないでよ、あんなオワコン」
(聞こえるんだけど・・・)
翼ちゃん記録2m15センチ!高校女子の記録更新!
「えええええええええええええ」
「すごすぎる!!さすが忍者!!!」
「あの野球バカよりも飛んでるじゃねーか!」
カイト「・・・・・・!!」
体育館の裏で落ち込むカイト。
翼「あ、こんなところに・・・
これカイトさんが好きな焼きそばパン・・・購買で買ってきました」
「ありがとう・・・」
「となりいいですか?」
「どうぞ」
「・・・・・・」
翼「あ・・・あの・・・」
カイト「・・・君はなんでもできるんだね・・・」
「そ、そんなことないですよ・・・
「ぼくには野球しかなかった・・・
両親がベイスターズの熱狂的ファンでね・・・
小さい頃から将来の夢はプロ野球選手と決まっていた・・・
親の期待に応えてこれでも頑張ったつもりさ・・・
それがこのざまだよ・・・
唯一の取り柄を自ら台無しにしてしまったのさ」
「カイトさん・・・」
「野球を辞めて以来、親とは口も聞いてない・・・なんか気まずくてね」
翼「・・・・・・」
相模高校野球部監督室。
北条監督「え?風間くんを部に戻せ?」
「お願いいたします監督殿・・・!」
「で、でもあの処分は、私だけじゃなくて学校理事会が決めたもので・・・その・・・」
「ではその理事会にかけあっていただけませんか??」
「い、いや~・・・しかしカイト君も余計なことするよ・・・
部内の揉め事に首を突っ込まなければ、うちの部も新聞沙汰にならずに甲子園に行けたのに・・・」
「部のいじめを見て見ぬ振りをすればよかったとおっしゃるのですか??」
「そういうわけじゃないけど・・・」
「ではカイトさんを部に戻していただけるんですね?」
「そういうわけでもないけど~・・・」
「・・・・指揮官としてあるまじき煮え切らない態度・・・!
かくなる上は・・・!」
刀を取り出す。
切腹しようとする翼「この翼の命と引き換えに~~!!」
悲鳴を上げる北条監督「ひ~!!」
マスコミの追求。
日本刀の所持はいつからなんですか!!
自殺の動機はなんだったんですか!!??
クラスでいじめがあったんですか!?
モンゴルへ行っちゃったりするんですか!!?
私の高校生活は終わった・・・
そしたら変な人が来た・・・
長門「は~はは・・・!切腹で新聞一面とは、かつて惚れた女として恥ずかしいぞソードダンサー!」
翼「な、なにしに現れたんですか!
この前カイトさんに退治されたのに、再び甲賀の里を・・・!?」
長門「何も言わずに我々についてきてもらおう」
翼「絶対嫌です」
長門「お前の親の頼みでもか?」
翼「え・・・?」
・
相模高校の廊下。
カイトのもとに集まってくる学生たち
「カイト君野球部復帰おめでとう!!」
「そういや、新聞読んだ?」
「いや~まさか本当に日本刀を所持していたなんて、やっぱり危ないやつだったんだね。退学になってよかった・・・」
「割腹自殺を試みたんだって・・・絶対頭病んでるよ」
「今年最後の夏、甲子園に連れてってね!応援してるから」
「・・・悪いけど自分の力で行ってくれ・・・」
「え?」
「オレは野球部には戻らない」
下駄箱に手紙が入っているのを見つける
「翼さん・・・!?」
手紙を開ける。
「そ・・・草書体で読めねえ!!!
これを読めるのは・・・」
『風と翼:REVIVE』登場人物
2018-06-25 20:53:29 (7 years ago)
5年ぶりの脚本公開!(マジか。)
でも、この脚本は漫画としてアップしたくてずっとあっためてたんだけど、読み切り用の『風と翼』をサイトに公開してマロさんに感想もらったら、案の定、創作意欲のモチベーションが天井知らずで、もういいやって細かい辻褄を最終確認して仕上げてしまいました。
現時点では、ソニックブレイドもいいけど、風と翼ブームがすごくて、というか、昔の自分の描いた漫画を読み返すのってすごい面白いのよ。内容全く忘れてるから。
この脚本も、だいたい作って、何年も放置だったんだけど、まあ、そりゃそうだよねっていう。前作よりもボリュームアップがすごくて、『80日間宇宙一周』みたいになっちゃってるんだよ。
ただ、今年の夏休みはなんらかの脚本を漫画にしようと思っているので、マロさんあたりのご意見を待っております。
風間カイト
元相模高校投手。野球をやめたことで学校に居場所がなくなる。
両親は熱狂的なベイスターズファンで、幼い頃から野球の英才教育を受ける。
そのため、野球選手が自分の夢だったのか、両親の夢だったのか自信をなくす。
今回、意外な職業に向いていることがわかる。
百地翼
元伊賀忍者最強のくのいち。カイトを慕って相模高校に転校する。
勉強についていけるか不安だったが意外とすぐに学校に溶け込む。
風間を学力と運動であっという間に追い抜き、一躍学校のアイドルになるが、風間の野球部復帰を監督に嘆願する際に切腹を試みたため、銃刀法違反で退学になる。
望月金吾
甲賀の総大将。あの百道丹波を一人前の忍者に育て上げ、彼と双璧をなす忍者だったが、野心がなかったため袂を分かつ。
おならの威力が年々弱まっており、自身の衰えを感じる。死ぬ前に孫の顔を見るのが夢。
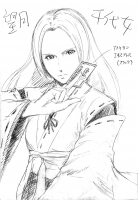
望月千代女
金吾の娘。田舎が嫌で駆け落ちした挙句にバツイチ。
現在は丸の内の外資系金融機関でOLをしているが、もともとは甲賀のくのいちであり、凄まじい式神使い。二つ名は歩き巫女。
長門守
伊賀の優秀なエージェント。
実は百道丹波が決めた翼の婚約者で、それがいやで翼は国を捨てた。
前回負けたリベンジに燃え、今回は気合十分だ。
織田信長
天才企業家。ついに信長自身が望月村に出陣する。その目的とは・・・
丹羽長秀
信長四天王。総務・法務担当。
常にペンと発注書を持ち、戦に必要な物資の補給に関しては天才的な働きをする。
見た目は人の良さそうなサラリーマン風の中年男だが、信長をして「鬼五郎左」と言わしめただけあって戦闘力は群を抜く。人情派の柴田と違って結構ドライな中間管理職。
わりとプレイボーイで若いお姉ちゃんが大好き。
柴田勝家
信長四天王。軍事担当。
文字通りの鋼の肉体を持ち、男らしさ、仁義を重んじる。矢が刺さってもわりと平気、骨密度測定不能、猛獣と会話できるなどという伝説から丹羽にゴリラ扱いされる。
明智博士
信長四天王。科学技術担当。マイペースな性格。信長の野望に疑念を持つ。
丹羽や柴田とは距離を置いているようだ。
北条氏政
相模高校野球部監督。臆病な性格。
カイトがいじめにクビをつっこまなければ暴力事件には発展しなかったと考える事なかれ主義者で「うじむし監督」と生徒にバカにされる。

北畠信雄
織田信長のご子息でボンボン。明らかにバカ息子。蝶ネクタイと七三が特徴。

百地丹波
伊賀の忍者を束ねる実力者で翼の父親。
利益のために織田信長と裏でつながり闇社会を動かしていた。
しかし、前作の失態で窮地に追い込まれる。
でも、この脚本は漫画としてアップしたくてずっとあっためてたんだけど、読み切り用の『風と翼』をサイトに公開してマロさんに感想もらったら、案の定、創作意欲のモチベーションが天井知らずで、もういいやって細かい辻褄を最終確認して仕上げてしまいました。
現時点では、ソニックブレイドもいいけど、風と翼ブームがすごくて、というか、昔の自分の描いた漫画を読み返すのってすごい面白いのよ。内容全く忘れてるから。
この脚本も、だいたい作って、何年も放置だったんだけど、まあ、そりゃそうだよねっていう。前作よりもボリュームアップがすごくて、『80日間宇宙一周』みたいになっちゃってるんだよ。
ただ、今年の夏休みはなんらかの脚本を漫画にしようと思っているので、マロさんあたりのご意見を待っております。
風間カイト
元相模高校投手。野球をやめたことで学校に居場所がなくなる。
両親は熱狂的なベイスターズファンで、幼い頃から野球の英才教育を受ける。
そのため、野球選手が自分の夢だったのか、両親の夢だったのか自信をなくす。
今回、意外な職業に向いていることがわかる。
百地翼
元伊賀忍者最強のくのいち。カイトを慕って相模高校に転校する。
勉強についていけるか不安だったが意外とすぐに学校に溶け込む。
風間を学力と運動であっという間に追い抜き、一躍学校のアイドルになるが、風間の野球部復帰を監督に嘆願する際に切腹を試みたため、銃刀法違反で退学になる。
望月金吾
甲賀の総大将。あの百道丹波を一人前の忍者に育て上げ、彼と双璧をなす忍者だったが、野心がなかったため袂を分かつ。
おならの威力が年々弱まっており、自身の衰えを感じる。死ぬ前に孫の顔を見るのが夢。
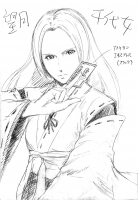
望月千代女
金吾の娘。田舎が嫌で駆け落ちした挙句にバツイチ。
現在は丸の内の外資系金融機関でOLをしているが、もともとは甲賀のくのいちであり、凄まじい式神使い。二つ名は歩き巫女。
長門守
伊賀の優秀なエージェント。
実は百道丹波が決めた翼の婚約者で、それがいやで翼は国を捨てた。
前回負けたリベンジに燃え、今回は気合十分だ。
織田信長
天才企業家。ついに信長自身が望月村に出陣する。その目的とは・・・
丹羽長秀
信長四天王。総務・法務担当。
常にペンと発注書を持ち、戦に必要な物資の補給に関しては天才的な働きをする。
見た目は人の良さそうなサラリーマン風の中年男だが、信長をして「鬼五郎左」と言わしめただけあって戦闘力は群を抜く。人情派の柴田と違って結構ドライな中間管理職。
わりとプレイボーイで若いお姉ちゃんが大好き。
柴田勝家
信長四天王。軍事担当。
文字通りの鋼の肉体を持ち、男らしさ、仁義を重んじる。矢が刺さってもわりと平気、骨密度測定不能、猛獣と会話できるなどという伝説から丹羽にゴリラ扱いされる。
明智博士
信長四天王。科学技術担当。マイペースな性格。信長の野望に疑念を持つ。
丹羽や柴田とは距離を置いているようだ。
北条氏政
相模高校野球部監督。臆病な性格。
カイトがいじめにクビをつっこまなければ暴力事件には発展しなかったと考える事なかれ主義者で「うじむし監督」と生徒にバカにされる。

北畠信雄
織田信長のご子息でボンボン。明らかにバカ息子。蝶ネクタイと七三が特徴。

百地丹波
伊賀の忍者を束ねる実力者で翼の父親。
利益のために織田信長と裏でつながり闇社会を動かしていた。
しかし、前作の失態で窮地に追い込まれる。
『風と翼』制作裏話
2018-06-18 22:42:56 (7 years ago)
-
カテゴリタグ:
- 漫画
あの『イノセントガーデン』の電撃公開から早三年…!再びカートゥーンのコンテンツがまさかの追加!・・・って、もう三年経つのかよ!!ひ~!
逆に言えば三年間も放置しているサイトをまだ見てくれる人がいるってのが嬉しいよ。このブログも20万アクセス行ったしな。中には、私ですら忘れている昔の記事とかを再読してくれる人(パキPさんとか)もいて、本当にありがとう。
でさ、いきなり話が飛ぶんだけどさ、とうとう恐竜ギャラリーが全て埋まったのよ。10年がかりで全80イラスト。ラストはベタにプテラノドンで〆ちゃったんだけど。これも海外の人とかがチェックとかしてくれてありがたかったんだけどね。当面はこれで終わりです。
で、その余ったリソースが今度は漫画に回せるようになったっていうね。ついに。そのリハビリとして10年前に描いて、アップするのが面倒で放置しっぱなしだった『風と翼』を公開することにしました。
10年前ってさ、少年マガジン用に短編を量産してた時代でさ。もう塑像乱造がひどくて、やりたい放題やって迷走した挙句、最後に『80日間宇宙一周』が出て来るってのが面白いんだけど。
そのひとつ前に描いたのが、この漫画なんだ。この漫画ってさ、設定がすごい難産だったってのを覚えてて、なぜならちょっと前に中世ヨーロッパの漫画の『ラストパーティ』をやってて、要は時代劇かぶりをしてたわけよ。
で、どうやって差別化するかすごい苦しんだんだ。忍者の国を守る天正伊賀の乱をベースにした奴がやりたかったんだけど、どうにも戦国時代って感情移入が難しくて、だってさ、基本的人権がない世界なわけじゃん。
そんな世界に違和感なく没入できるやつってサイコパスだけというか、まともな現代人の読者だったら抵抗を感じるはずなんだよ。これが参ってさ。
天正伊賀の乱ってさ、ネタバレするとさ、結局織田信長が伊賀忍者を蹴散らしちゃうんだよ。それだけ聞くと、やっぱりあの天魔王は残虐だなって感じがするけどさ、伊賀忍者もかなりヤバイ集団で、本当にてめえら人の命をなんだと思ってんだくらいのこと平気でやってるのよ。
対立する勢力の双方に自分の忍びを派遣して殺し合わせちゃったりしてさ。とてもじゃないけど、こいつらを主人公にしても、がんばれ伊賀忍者!とか、織田信長に負けるな!ってならないわけよ。
で、すっごい悩んで、専守防衛をモットーとする忍者のもうひとつの勢力の甲賀忍者の話にしようと。でも、翼ちゃんとか、もうキャラ設定とかデザインしちゃってて、この子を没にするのはけっこうもったいないな、と。
じゃあ、甲賀の忍者にしちゃえ、あ、でも甲賀ってくノ一がいないんだよな、なら移籍させようってことにしました。
さらに、時代設定もさ、スーファミからの『がんばれゴエモン』みたいに、現代的なテイストのある時代劇を考えてたんだけど、それだと『ラストパーティ』とあんまり差別化できないってことに気づいて、逆をやってみたんだ。
つまり、時代劇テイストの現代劇っていうね。これって意外と新しいんじゃないかってことで採用したんだ。利潤追求主義が跳梁跋扈し、年間の自殺者が三万人も出る現代の日本も、考えようによっちゃあ戦国時代と言えなくもないし。
しかし、冒頭のシーンなんかは、今だと日大アメフト部の問題なんかに通じるけど、当時は朝青龍の八百長問題だったんだよねwこの時の講談社本社ビルは、いろいろあって警備が厳重だったのを覚えています。
「風間カイト」
モデルは風魔小太郎。そのためか結構背が高い。おそらくダルビッシュくらい。自分の漫画ではなにげに珍しい運動神経がいい主人公。
頭は悪いんだけど、けっこういい人というか、優しい人っていう感じにした。日大の問題とか見ると、体育会系ってヒエラルキーが強固な暴力集団なのかって感じもするけど、これはどの分野の世界でもそうだけど、こういう嫌なやつって結構中途半端っていうか、ある程度のレベルになるといい人が多いって感じあるしな。なんかオタクってスポーツマン目の敵にするけどね。偏見はよくないよねっていう。
この漫画ってさ、主役のふたりはどっちもスティグマ(傷)があるんだよね。で、ここら辺は、続きをもし描くことがあったら掘り下げたいんだよね。
カイトくんは小さい頃から親に「横浜ベイスターズのプロ野球選手になれ!」っていう圧力がすごくて、少年野球とかやらされててさ、翼さんはそれこそ、親の百地丹波に冷酷非道なプロの忍者として育てられちゃったわけで。境遇が似てるんだよね。
だからさ、続きはさ、甲賀忍者と伊賀忍者が織田信長と戦うために共闘するんだよね。そうなると翼の親は出てくるよなって。で、むき卵頭領のライバルとしてね。
「百地翼」
モデルは『サガフロンティア』ってRPGゲームの雑魚キャラ。なぜかスライムみたいなポジションに美少女キャラが出てくるんだよw
最後の殺陣を引き立たたせたかったから、すっごい臆病で弱そうに描いた。絶対暴力の世界とは程遠いだろっていう。そう見せといて、結構すごい忍者だったっていう。スポーツ漫画とかでこういう展開多いよね。『カーズ』のドッグ・ハドソンとか。
続編だと、忍者の世界しか知らない彼女が、全然高校生として馴染めない、みたいな展開やりたいね。全然友達ができない!みたいな。普通の女子高生のカルチャーにまるで無知みたいな。
「望月頭領」
モデルは麿赤児さん。『魁!男塾』で江田島塾長をやった人。確かに似ているw
『合い言葉は勇気』の麿赤児さんが好きで、なんか昭和初期の格好しててかっこいいんだよな。帽子とか杖とかが。
ちなみに次作の『80日間宇宙一周』では『合い言葉は勇気』の津川雅彦さんが出てるんだよね。どんだけ好きなんだっていう。
頭に手裏剣刺さってるシーンは描いてて自分で笑ってたなあ。
「長門守」
有名な伊賀忍者の藤林長門守(ふじばやしながとのかみ)から。
恐ろしい殺し屋って設定だったんだけど、ちょっと抜けてるというか、天然みたいになっちゃった。これは全くの想定外です。なんか、全体的にノリがギャグマンガに振りすぎちゃったっていうのはあるよね。それもこれもハゲのせい。
「織田信長」
この続きとして、天正伊賀の乱っぽくなってくんだよね。信長がなんでここまであの土地に執着するのかっていう謎もあるし。
実は、あの土地の土壌に秘密があった、とかね。ウランよりもすごい核兵器がつくれるレアメタルが埋まっててもいいし、あの薬草の調合方法によっては、不老不死の秘薬もできるとかでもいいよな。こういうのってマクガフィンだからね。
でもさ、昨今の米朝首脳会談とか見てるとさ、核問題をやりたいなって感じもある。もう、一部の国だけチート武器持っているのがフリートレード上よくない!みたいに、信長は国連加盟国の数(193発分)だけ核ミサイルを作ってさ、それを全ての国に配分しちゃうみたいな、めちゃくちゃな野望を考えててもいいよな。核の楽市楽座じゃ!みたいな。意味不明か。
ちなみに、信長のモデルは俳優の山崎一さん。柴田勝家は角田信朗さん。丹羽長秀は奇跡のキャスティングとなった小日向文世さんです。
で、この漫画って設定的に、戦国武将を史実を無視して好きなだけ出せるのがいいよね。北条早雲とか謙信と信玄とか。言ってみれば、戦国武将版のジュラシック・パークだよな。
でもまあ、今後はカートゥーンの残りの、『優等生学』とか『トカノマン』をアンロックする予定です。目指せコンプリート!(長編の『青春アタック』がかなり厳しいが)
逆に言えば三年間も放置しているサイトをまだ見てくれる人がいるってのが嬉しいよ。このブログも20万アクセス行ったしな。中には、私ですら忘れている昔の記事とかを再読してくれる人(パキPさんとか)もいて、本当にありがとう。
でさ、いきなり話が飛ぶんだけどさ、とうとう恐竜ギャラリーが全て埋まったのよ。10年がかりで全80イラスト。ラストはベタにプテラノドンで〆ちゃったんだけど。これも海外の人とかがチェックとかしてくれてありがたかったんだけどね。当面はこれで終わりです。
で、その余ったリソースが今度は漫画に回せるようになったっていうね。ついに。そのリハビリとして10年前に描いて、アップするのが面倒で放置しっぱなしだった『風と翼』を公開することにしました。
10年前ってさ、少年マガジン用に短編を量産してた時代でさ。もう塑像乱造がひどくて、やりたい放題やって迷走した挙句、最後に『80日間宇宙一周』が出て来るってのが面白いんだけど。
そのひとつ前に描いたのが、この漫画なんだ。この漫画ってさ、設定がすごい難産だったってのを覚えてて、なぜならちょっと前に中世ヨーロッパの漫画の『ラストパーティ』をやってて、要は時代劇かぶりをしてたわけよ。
で、どうやって差別化するかすごい苦しんだんだ。忍者の国を守る天正伊賀の乱をベースにした奴がやりたかったんだけど、どうにも戦国時代って感情移入が難しくて、だってさ、基本的人権がない世界なわけじゃん。
そんな世界に違和感なく没入できるやつってサイコパスだけというか、まともな現代人の読者だったら抵抗を感じるはずなんだよ。これが参ってさ。
天正伊賀の乱ってさ、ネタバレするとさ、結局織田信長が伊賀忍者を蹴散らしちゃうんだよ。それだけ聞くと、やっぱりあの天魔王は残虐だなって感じがするけどさ、伊賀忍者もかなりヤバイ集団で、本当にてめえら人の命をなんだと思ってんだくらいのこと平気でやってるのよ。
対立する勢力の双方に自分の忍びを派遣して殺し合わせちゃったりしてさ。とてもじゃないけど、こいつらを主人公にしても、がんばれ伊賀忍者!とか、織田信長に負けるな!ってならないわけよ。
で、すっごい悩んで、専守防衛をモットーとする忍者のもうひとつの勢力の甲賀忍者の話にしようと。でも、翼ちゃんとか、もうキャラ設定とかデザインしちゃってて、この子を没にするのはけっこうもったいないな、と。
じゃあ、甲賀の忍者にしちゃえ、あ、でも甲賀ってくノ一がいないんだよな、なら移籍させようってことにしました。
さらに、時代設定もさ、スーファミからの『がんばれゴエモン』みたいに、現代的なテイストのある時代劇を考えてたんだけど、それだと『ラストパーティ』とあんまり差別化できないってことに気づいて、逆をやってみたんだ。
つまり、時代劇テイストの現代劇っていうね。これって意外と新しいんじゃないかってことで採用したんだ。利潤追求主義が跳梁跋扈し、年間の自殺者が三万人も出る現代の日本も、考えようによっちゃあ戦国時代と言えなくもないし。
しかし、冒頭のシーンなんかは、今だと日大アメフト部の問題なんかに通じるけど、当時は朝青龍の八百長問題だったんだよねwこの時の講談社本社ビルは、いろいろあって警備が厳重だったのを覚えています。
「風間カイト」
モデルは風魔小太郎。そのためか結構背が高い。おそらくダルビッシュくらい。自分の漫画ではなにげに珍しい運動神経がいい主人公。
頭は悪いんだけど、けっこういい人というか、優しい人っていう感じにした。日大の問題とか見ると、体育会系ってヒエラルキーが強固な暴力集団なのかって感じもするけど、これはどの分野の世界でもそうだけど、こういう嫌なやつって結構中途半端っていうか、ある程度のレベルになるといい人が多いって感じあるしな。なんかオタクってスポーツマン目の敵にするけどね。偏見はよくないよねっていう。
この漫画ってさ、主役のふたりはどっちもスティグマ(傷)があるんだよね。で、ここら辺は、続きをもし描くことがあったら掘り下げたいんだよね。
カイトくんは小さい頃から親に「横浜ベイスターズのプロ野球選手になれ!」っていう圧力がすごくて、少年野球とかやらされててさ、翼さんはそれこそ、親の百地丹波に冷酷非道なプロの忍者として育てられちゃったわけで。境遇が似てるんだよね。
だからさ、続きはさ、甲賀忍者と伊賀忍者が織田信長と戦うために共闘するんだよね。そうなると翼の親は出てくるよなって。で、むき卵頭領のライバルとしてね。
「百地翼」
モデルは『サガフロンティア』ってRPGゲームの雑魚キャラ。なぜかスライムみたいなポジションに美少女キャラが出てくるんだよw
最後の殺陣を引き立たたせたかったから、すっごい臆病で弱そうに描いた。絶対暴力の世界とは程遠いだろっていう。そう見せといて、結構すごい忍者だったっていう。スポーツ漫画とかでこういう展開多いよね。『カーズ』のドッグ・ハドソンとか。
続編だと、忍者の世界しか知らない彼女が、全然高校生として馴染めない、みたいな展開やりたいね。全然友達ができない!みたいな。普通の女子高生のカルチャーにまるで無知みたいな。
「望月頭領」
モデルは麿赤児さん。『魁!男塾』で江田島塾長をやった人。確かに似ているw
『合い言葉は勇気』の麿赤児さんが好きで、なんか昭和初期の格好しててかっこいいんだよな。帽子とか杖とかが。
ちなみに次作の『80日間宇宙一周』では『合い言葉は勇気』の津川雅彦さんが出てるんだよね。どんだけ好きなんだっていう。
頭に手裏剣刺さってるシーンは描いてて自分で笑ってたなあ。
「長門守」
有名な伊賀忍者の藤林長門守(ふじばやしながとのかみ)から。
恐ろしい殺し屋って設定だったんだけど、ちょっと抜けてるというか、天然みたいになっちゃった。これは全くの想定外です。なんか、全体的にノリがギャグマンガに振りすぎちゃったっていうのはあるよね。それもこれもハゲのせい。
「織田信長」
この続きとして、天正伊賀の乱っぽくなってくんだよね。信長がなんでここまであの土地に執着するのかっていう謎もあるし。
実は、あの土地の土壌に秘密があった、とかね。ウランよりもすごい核兵器がつくれるレアメタルが埋まっててもいいし、あの薬草の調合方法によっては、不老不死の秘薬もできるとかでもいいよな。こういうのってマクガフィンだからね。
でもさ、昨今の米朝首脳会談とか見てるとさ、核問題をやりたいなって感じもある。もう、一部の国だけチート武器持っているのがフリートレード上よくない!みたいに、信長は国連加盟国の数(193発分)だけ核ミサイルを作ってさ、それを全ての国に配分しちゃうみたいな、めちゃくちゃな野望を考えててもいいよな。核の楽市楽座じゃ!みたいな。意味不明か。
ちなみに、信長のモデルは俳優の山崎一さん。柴田勝家は角田信朗さん。丹羽長秀は奇跡のキャスティングとなった小日向文世さんです。
で、この漫画って設定的に、戦国武将を史実を無視して好きなだけ出せるのがいいよね。北条早雲とか謙信と信玄とか。言ってみれば、戦国武将版のジュラシック・パークだよな。
でもまあ、今後はカートゥーンの残りの、『優等生学』とか『トカノマン』をアンロックする予定です。目指せコンプリート!(長編の『青春アタック』がかなり厳しいが)
- Calendar
<< January 2026 >> Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- search this site.
- tags
-
- 漫画 (387)
- 脚本 (243)
- 映画 (235)
- 雑記 (163)
- ゲーム (156)
- 本 (116)
- 教育 (107)
- 生物学 (105)
- 科学 (93)
- 社会学 (81)
- 歴史 (72)
- テレビ (71)
- 芸術 (61)
- 政治 (50)
- 数学 (40)
- 進化論 (40)
- 資格試験 (38)
- 情報 (38)
- サイト・ブログ (37)
- 語学 (37)
- 映画論 (36)
- 物理学 (33)
- 哲学 (32)
- 恐竜 (29)
- 育児 (28)
- 文学 (26)
- 化学 (25)
- 論文 (22)
- PIXAR (22)
- 心理学 (18)
- 地学 (16)
- 気象学 (15)
- 地理学 (15)
- 技術 (13)
- 経済学 (12)
- 医学 (11)
- 玩具 (9)
- 司書 (8)
- 法律学 (7)
- 対談 (5)
- スポーツ (4)
- 映画の評価について (1)
- プロフィール (1)
- archives
-
- 202601 (2)
- 202512 (4)
- 202511 (15)
- 202510 (8)
- 202509 (5)
- 202508 (3)
- 202507 (3)
- 202506 (3)
- 202505 (1)
- 202504 (2)
- 202503 (2)
- 202502 (2)
- 202501 (1)
- 202412 (2)
- 202411 (6)
- 202410 (2)
- 202409 (4)
- 202408 (4)
- 202407 (7)
- 202406 (27)
- 202405 (11)
- 202404 (4)
- 202403 (23)
- 202402 (22)
- 202401 (15)
- 202312 (4)
- 202311 (7)
- 202310 (2)
- 202309 (8)
- 202308 (9)
- 202307 (8)
- 202306 (5)
- 202305 (15)
- 202304 (4)
- 202303 (4)
- 202302 (2)
- 202301 (4)
- 202212 (15)
- 202211 (7)
- 202210 (5)
- 202209 (4)
- 202208 (4)
- 202207 (7)
- 202206 (2)
- 202205 (5)
- 202204 (3)
- 202203 (2)
- 202202 (5)
- 202201 (6)
- 202112 (6)
- 202111 (4)
- 202110 (6)
- 202109 (7)
- 202108 (5)
- 202107 (8)
- 202106 (4)
- 202105 (8)
- 202104 (4)
- 202103 (6)
- 202102 (10)
- 202101 (3)
- 202012 (12)
- 202011 (3)
- 202010 (4)
- 202009 (5)
- 202008 (6)
- 202007 (4)
- 202006 (4)
- 202005 (4)
- 202004 (7)
- 202003 (5)
- 202002 (6)
- 202001 (8)
- 201912 (6)
- 201911 (5)
- 201910 (3)
- 201909 (4)
- 201908 (10)
- 201907 (3)
- 201906 (6)
- 201905 (10)
- 201904 (3)
- 201903 (7)
- 201902 (8)
- 201901 (5)
- 201812 (7)
- 201811 (12)
- 201810 (7)
- 201809 (5)
- 201808 (10)
- 201807 (5)
- 201806 (19)
- 201805 (14)
- 201804 (11)
- 201803 (15)
- 201802 (4)
- 201801 (6)
- 201712 (4)
- 201711 (3)
- 201710 (11)
- 201709 (9)
- 201708 (15)
- 201707 (7)
- 201706 (4)
- 201705 (5)
- 201704 (6)
- 201703 (7)
- 201702 (6)
- 201701 (3)
- 201612 (3)
- 201611 (7)
- 201610 (7)
- 201609 (2)
- 201608 (8)
- 201607 (8)
- 201606 (7)
- 201605 (3)
- 201604 (4)
- 201603 (8)
- 201602 (3)
- 201601 (2)
- 201512 (3)
- 201511 (3)
- 201510 (4)
- 201509 (4)
- 201508 (8)
- 201507 (17)
- 201506 (2)
- 201505 (5)
- 201504 (9)
- 201503 (20)
- 201502 (7)
- 201501 (4)
- 201412 (5)
- 201411 (3)
- 201410 (2)
- 201409 (3)
- 201408 (3)
- 201407 (3)
- 201406 (12)
- 201405 (6)
- 201404 (7)
- 201403 (5)
- 201402 (12)
- 201401 (9)
- 201312 (6)
- 201311 (9)
- 201310 (8)
- 201309 (6)
- 201308 (6)
- 201307 (6)
- 201306 (10)
- 201305 (10)
- 201304 (23)
- 201303 (17)
- 201302 (16)
- 201301 (5)
- 201212 (10)
- 201211 (4)
- 201210 (18)
- 201209 (4)
- 201208 (30)
- 201207 (7)
- 201206 (4)
- 201205 (6)
- 201204 (4)
- 201203 (4)
- 201202 (3)
- 201201 (3)
- 201112 (4)
- 201111 (7)
- 201110 (3)
- 201109 (9)
- 201108 (3)
- 201107 (7)
- 201106 (2)
- 201105 (11)
- 201104 (7)
- 201103 (14)
- 201102 (19)
- 201101 (27)
- 201012 (25)
- 201011 (70)
- 201010 (34)
- 201009 (30)
- 201008 (42)
- 201007 (44)
- 201006 (29)
- 201005 (37)
- 201004 (50)
- 201003 (44)
- 201002 (48)
- 201001 (38)
- 200912 (20)
- recent trackback
- others
-
- RSS2.0
- hosted by チカッパ!
- HEAVEN INSITE(本サイト)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356